TOP > 二、室町幕府雑学記 > 2 続・室町幕府の前半戦
小見出し
「幕府創生、本当のところ」
「もう一人の将軍」
「東国へ駆ける」
「さよなら、俺らの聖地鎌倉」
「西へ」
「夢を見ていたんだ、きっと…」
「たどり着いた場所」
「始まった未来」
2 続・室町幕府の前半戦
さて、いよいよ、今度こそ本当に室町幕府の始まりです。
「始まりです(キリッ」とか言っといてなんですが、
室町時代というのは、始まりもそして終わりも実に曖昧です。
開始は「南北朝期」、終盤は「戦国期」と重なって、真の姿が見えづらい!
いやむしろ、最初から最後までその姿を変え続けていったのではないか?
…と思われる程に、掴みづらい!
にもかかわらず、250年間確かに存在し続けた、無いしかし在る、
そんな禅問答のような幕府の実態に迫るのがこのサイトの目標の一つですが、
世間一般のイメージがあまり宜しくないのが残念なところであります。
いや、イメージ悪いどころかむしろ、みんな気にしていない。一億総スルー幕府。
戦国期に至っては、なんかもう無かったことにされてる始末。
やれ「天下統一だー」とか、「上洛だー」とか、…え? 何それ、ちょっと待て、
あるから! まだ幕府あるから!! しかも結構やる気もあるからっ!!
戦国期と言うと、各地で大名達が敵対し、ひたすら奪い合いの戦ばっかやってた、
…ってイメージが強いかもしれませんが、
実は、自国(分国)に平和と繁栄を築き、隣国との "協調関係" を重んじていた大名も少なくないのです。
(※この時代の「国・分国」とは、今でいう都道府県です。やや区画は異なりますが。)
そして、そういう国の大名は総じて、幕府と良好な関係を保っていました。
彼らは、"私利" を戒め "公利" を重んじ、奪う勢力から自国を守る為に戦い、
中心である幕府もまた、秩序を維持する存在でありました。
しかし、やはり守る戦いというのは不利なもの。
力のままに隣国を欲して領土拡大を進める新興勢力の、
ルール無き武力の破壊力に、世は乱されていきます。
悲しいかな、覇者の勝利が戦国の結末となってしまいましたが、
しかし一方で、道理ある天下を最後まで諦めず、その非道に立ち向かい散っていった者達がいて、
彼らの信念は、例え一時(いっとき)だとしても確かに、戦国の闇に黎明(夜明け)の明かりを投げ掛けたのです。
(…でもイマイチちゃんと評価されてないよねー。
戦国期の道義ある武家こそ、もっとみんなに知られて愛されて欲しいのに。
ひと言に天下統一と言っても、「恫喝による天下統一」と「道徳による天下統一」では、
天と地ほどの差があります。
「武士」とは本来、武力で天下を奪う外道ではなく、「徳で天下を安んずる君子である」と言う事を、
これから先の解説で、きっと分かってもらえると思います。)
まあそんな訳で、いま一度、幕府を中心とした視点で、
自国を思い、他国を思い、天下を思い続けたまともな諸国の大名との関係からこの時代を見直してみたら、
これまでとは全く違った、そしておそらく "本当の世界の姿" が見えてくると思います。
(※戦国期の社会に関しては、
これまで主流だった、戦国大名を個別に見ていく「群雄割拠」的な捉え方から、
幕府を中心に、天下を包括的に捉える方向へ、近年、見直しが進められています。
「秩序が無かった」と思われてきた戦国の社会にも、実は「秩序があった」という訳です。
虚実入り乱れて誤解の多い戦国期の真の姿に迫る、歓迎すべき研究の数々が蓄積しつつあります!
…がしかし、このサイトでメインに扱うのは、戦国期の前段階の時代です。)
このように、不当なまでに存在感の薄い幕府ではありますが、
ほんの一歩踏み込んでみると、実に奥深かったりするんです。
なぜならそれは…どことなく緩かったからw
「ゆるゆるで結局戦乱引き起こされてたんじゃ、元も子もねーだろ!」と、まぁそれはそうなのですが、
肯定的に見ればこの緩さ、その時代の社会が求めるものを自在に反映できる柔軟さとも取れるのです。
そしてそれは、始まりの初代将軍足利尊氏(あしかが たかうじ)の時点で、
紛れもなくゆるゆるだったことに起因します。
彼はどうやら、利己的な野心とか権威への強欲でもって行動していたのではなく、
言ってみれば、「天性で時代に応えちゃった」みたいなところがある人です。
そんなんで始まってしまった室町幕府。
確かに、腑甲斐無い所もありましたし、頼りの無さも否めません。
それでも、その柔軟さで移りゆく世と共に果敢に姿を変え、その緩さは人や文化の "流れ" を作りました。
室町時代半ばに花開いた『東山文化』が、
今日の私たちの心に最も深く染み入る日本文化であるのは、
そんな緩さの中から、人々の心を直に反映して必然的に生まれて来たものだったからだと思うのです。
だとしたら、文化のみならず「国や社会の在り方」「人々の意識」についても、
過去に忘れた、本来の自然で根源的な部分を、この時代の中に見出せるんじゃないかと思います。
それでは、これまでちょっと(いやかなり)誤解されて来た「室町幕府が始まった頃」の話を、
いま一度、真実に沿って描き直してみたいと思います。
「幕府創生、本当のところ」
鎌倉幕府が終焉を迎えたのが元弘3年(1333)。
得宗(執権北条一族の総領)による行き過ぎてしまった専制政治によって、各地で噴出しつつあった矛盾や反発が、
倒幕へと向かう一つの激流となったその契機は、やはり後醍醐天皇の強烈な個性と不屈の精神にあったと思われます。
しかし幕府解体後、早速政治の中心を京都に戻して始めた天皇による親政は…ちょっと強烈過ぎました。
強い信念と情熱を掲げて推し進めた『建武の新政』ではありますが、
強力な主導権を背景に、次々に打ち出された斬新な政策は、
どれも時代にそぐわず、人々(武家だけでなく公家社会も)の混乱と反発を招きます。
(当時の社会を痛烈に風刺した長歌、「この頃都に流行るもの…」で始まる有名な『二条河原の落書』は、
この頃作られたもの。(※落書(らくしょ)…匿名のらくがき)
京童を装って、世上への嘆きや憤りをユーモアで訴えた、知識人たちの "仕業" です。)
そんな新政権への不満が募る中、いつのまにかその不満の受皿になっていたのが足利尊氏だった訳です。
彼は、もともと鎌倉幕府の御家人だったのですが、
末期の北条得宗家に対しては、武家社会でも不満が募っていて、
彼らの期待と家臣の後押しを背景に、後醍醐天皇による倒幕の呼びかけに応じて幕府に反旗を翻します。
足利尊氏の挙兵には多くの諸国の武士が馳せ参じ、結果、倒幕は達成されるのです。
(鎌倉幕府は源頼朝によって開かれたものだが、政争により3代で源氏の将軍が途切れた後、
源頼朝の外戚だった北条一族(平氏)が幕府を乗っ取り…じゃなかったw、実権を握ることとなり、
源(みなもと)将軍家断絶後の源氏嫡流後継者である足利家は、長らく日陰時代を過ごしていた。
ただし、諸国の武士たちの源氏将軍への潜在的な期待感は、水面下で保たれ続けていたのでしょう。)
さて、大いに戦功をあげた彼ら旧幕府勢は、以後、新政権の一員となるのですが、
しかし、混迷を極める天皇親裁体制の中、
もともと武士たちからの支持が高かった足利尊氏は、やがて――― 謀殺の対象とされてしまうのです。
まあ、武家政権復活の恐れがあるとしたら、最も近い所にいる一人であった訳だし、
危険人物認定されるのも、そして戦わねばならない日が来るのも、時間の問題だったのかも知れませんが、
それでも、新政権からの離脱のきっかけを作り、武家政権立ち上げまでの道を走らせたのは、
欲望を秘めた周到な計画性ではなく、偶然の連なった「運命」であったと言えるでしょう。
なぜって、武士である足利尊氏は、もともと天皇に弓を引く気などさらさら無く、
例えば、鎌倉での反乱鎮圧後、上洛の命令があれば、(命狙われてんのに)素直に京都に帰ろうとするし、
後醍醐天皇から追討対象にされた折には、寺に引き篭もって出家を企てる始末w
それでも、乱れゆく政道は正されるべきであり、導く "誰か" が必要だったのです。 (※政道…政治の道。)
尊氏追討の勅命(ちょくめい。天皇の命令)を受けた新田義貞に打勝ち、
東国(鎌倉)から一転、西国(九州)まで進撃、
そして一気に諸国の武士を束ね、"時" と "勢" と "命(めい)" の全てを味方につけて駆け抜けたその先には、
持明院統の光厳上皇、光明天皇を奉じての入京という「凱旋」が、新しい時代の幕開けと共に待っていたのです。
『建武式目』を制定した建武3年(1336)、京都に武家政権が誕生することとなったのは、
決して一支配者の独断によるものではなく、
時代の声に押されながら、天下が自然とそこへ流れ着いた、その結果でした。
というのも、この足利尊氏という人、実におおらかな性格だったそうな。
戦で軽く死にそうになっても、まるで余裕、恐れるどころか笑ってる。
裏切り者も怨むべき敵も、我が子のように許しちゃう。
財貨に執着なし。山のような貰い物もどんどん人にあげちゃう。残らずあげちゃう。
心は、強く大きく慈悲深い。
ただ、傍から見ると一見成り行き任せで、やや言動が予測不能なところもあったようですがw
でも、そんな柔軟性と適応力が『武家の棟梁』たるべき天性に結びついて、天下を導くことになった、そんな人。
つまり、ある意味、世の人々の合意の上に成り行きで始まっちゃった感がある室町幕府ですから、
緩いのもまぁ、当然っちゃあ当然なんですが、
「権力基盤弱いよね」とか、しょっちゅう言われて涙目です。
にもかかわらず、250年も続いたのですよ。
やはりここは、その "不思議" に迫るべきだと思います。
室町幕府とは、一体何だったのか?
まぁ、今のところは、
「絶対的な権力を持つ支配者が、意のままに振舞う政権ではなく、
諸大名の合議のもと、将軍個人の私利ではなく天下の公利を求めて模索(いや、迷走)し続けた政権」
とだけ言っておきましょう。(…続きは、徐々に明らかになる、はず。)
それにしてもなぜ、
強固な意志を持って進められた天皇親政ではなく、成り行きで再開したとも言える武家政権が定着したのか?
思うにそれは、前者が自らが理想とする制度を掲げてそれに "世の中が従うべき" としたのに対し、
後者が、その時代が求める政治の形に従った、すなわち "世の中に従った" ものだったからでしょう。
最も多くの民意を掬(すく)える政権に、時代という "流れ" がたどり着いた必然だったのです。
(まあ、簡単に言うと行き当たりばった…(以下略)
供給より需要、制度より民意が先立つ政権だった、とも言えると思います。)
ただし、この時代に後醍醐天皇の果たした役割が非常に大きかったのは紛れもない事実ですし、
その人物の偉大さは、
北畠顕家(きたばたけ あきいえ)のような忠臣かつ諫臣(かんしん)の存在が、証明していると思います。
(※諫臣…諫言(かんげん)する臣。 諫言とは、目上の人の非を諫(いさ)めること。またその言葉。)
諫言と言うものは、
自己の利害を顧みず、ただ純粋に主君の為を思ってするものですから、
諫臣こそ、最大の忠義を持った臣と言える訳で、
奸臣や佞臣(ねいしん)…つまり、自分の利益や保身だけを目当てに主君に媚び諂(へつら)い、
ひたすら追従するしか能の無い者達とは、対極にある存在です。
北畠顕家は後醍醐天皇に対し、
新政権の過ちを、強くそして真摯に諫めた書状を奏上し、
その7日後に、足利軍との戦闘の中に散って行きました。
新政権の行く末を真に憂い、天下を思い、
そして最後まで戦いの中に忠義を尽くした北畠顕家のような忠臣の諫言こそ、
(新政権側で)本当は第一に賞賛されるべき美徳であるはずなのです。
(「どんなに政道が乱れようが、天皇に諫言する無礼者など忠臣とは呼べない!」と思う方もいるでしょうか?
しかし、北畠顕家の奏状に綴られた、
「私(し)を忘れて君(きみ)を思い、悪を却(しりぞ)け正に帰せんと欲するの故なり」
という言葉に、私はこれ以上無い最高の忠義を感じます。
(※ここでいう「悪」とは、後醍醐天皇の周囲にあって政道を乱す奸臣・佞臣のこと。(足利軍ではない))
天皇を敬うのと同じように、国をも想うのが真の忠臣。
そして実は、敵である足利軍とて、同じ思いを抱いていたのです。)
(※ちなみに、『北畠顕家奏状』については…
【『日本思想大系22 中世政治社会思想 下』(岩波書店)1981】
この奏状からは、新政権が重ねてしまった過ちと共に、
北畠顕家が非常に高い教養と、正しき政道への慧眼を持ち合わせていたことが読み取れます。
北畠家は本来公家なのですが…顕家は名武将です。 足利軍は相当苦しめられましたw
公家で名将で頭良くて、その上享年21歳って…ほんとどうなってんでしょうか。
この奏状も、若年とはとても思えない、かっこいい文章です。
ってか、現代人じゃその3倍生きたってこんなん書ける奴いねーよ!ってレベルです。一回読んどけ、ちびるぞ。
そんな桁外れな人物が多いのも、この時代の面白いところですが…
知名度の低さも桁外れ、ほんとどうなってんでしょうかw)
一方、「足利尊氏は後醍醐天皇に逆らった! 室町幕府は "天意に反した" 幕府だ!」という見方も、
あまりに一方的に過ぎると思います。 (※天意…天皇の意志)
建武の新政の挫折から室町幕府樹立までの過程を、公平な立場から本気で調べれば、
尊氏が後醍醐天皇を「裏切った」「反逆した」などという評価が妥当ではないことは、
誰しもすぐに気付くと思います。
(事の真相は… 当代随一の "とある高僧" の語録に記されています。
尊氏擁護の為に、私が勝手に捏造妄想している訳ではないので安心して下さいw
この "語録" については後々どこかで解説しますが、
建武の新政が民意の大反発で早々に挫折した背景には、
一つに、政策が強引過ぎたことが挙げられますが、
(※後醍醐天皇が目指した体制は、
武家を排除した「鎌倉以前の貴族政治への回帰」(=律令制以来の、天皇と貴族が牽制し合う支配体制)
と誤解されている事がありますが、
実際は、既存の貴族層をも解体した「天皇直属の官僚組織の創出による、徹底した君主への集権制」
という、革新的な体制です)
しかし、その改革の中で、
後醍醐天皇の周辺の近臣たちが、富と権力に執心して好き勝手やり過ぎたことが、
新政権の瓦解時期を、急激に早める結果を生むのです。
(圧倒的な権勢に、巨万の富…と、とにかく凄かったらしいw
もちろん政治に口出しまくりで、もう完全無法状態。
道理や公正、あるいは民のため…なんて概念は無く、
自分たちが天下の利権を有りったけ独占する事に命を懸けていた模様…orz)
そんな、欲に溺れて傲慢になった者達は―――
邪魔者の排除に手段を選びません。
讒言(ざんげん。人を陥れる為の嘘)によって嵌められ葬られた者は少なくなく、
"嘘" と "欲" が絡み合い、新政権は内部からもメチャメチャになりつつあったのです。
足利尊氏も讒言で嵌められた中の一人。
ただ、彼は生き延びた。 多くの武士たちの支持があったから。
理不尽に殺されかけて、抵抗したら裏切り者だ!逆臣だ!とは…あんまりですw ほかにどうしろと?
彼がそうせざるを得なかった理由を、新政権の内外の実状を、どうか公平な目で再考して欲しい。
尊氏を「反逆者」と呼んで、新政権挫折の原因の全てを彼に着せるのは、正しい判断ではない。
真の逆臣は、その欲心で新政権を崩壊に導いた奸臣たちであるはずです。
忠臣北畠顕家も、政治を汚(けが)す奸臣を除くよう、強く主張していました。
実際、尊氏自身は、最後まで後醍醐天皇を慕っていた(慕っていたかった)のは事実だし、
正直…、尊氏がどんなに拒んでも、他の誰かにその代わりは担えなかったでしょう。
時代の宿命に因る所の大きい、希望と悲しみの混在する誰にも止められない "流れ" だったのです。
(北畠顕家でさえ、
「政道がこのまま改められないのなら、陛下のもとを去って隠遁する。
(…だからどうか、愚かな私の懇情を聞き届けてくれ!)」
と決意するほどに、世は乱れていたのです。
当時の現状を知れば、尊氏を責めるのは筋違いである事が分かると思います。)
…ただし、
どんな理不尽な理由があったとしても、抵抗したら逆臣の汚名を免れない事もまた、当時の現状でした。
それでも、いま目の前に、苦しみあえぐ民がいるのなら、
自らの犠牲など微塵も躊躇(ためら)わず、
正しき政道一つを信じ、ただひたすら国の明日を案じて突き進んだ信念の武士 ―――
…って実はそれ、尊氏って言うより "もう一人の将軍" なんですがw )
そしてもう一つ、鎌倉から室町へ、時代が激動した根本原因の一つに、
鎌倉時代後期に始まった「皇統の分裂」という、重大な問題がありました。
(※以前から皇統は "持明院統" と "大覚寺統" の二つに分裂し、両統迭立の不安定な状態が久しく続いていた。)
実は、後醍醐天皇が「打倒鎌倉幕府」を掲げて蜂起したのは、
「武家から政権を取り戻し、天皇親政の国家体制を確立する」という目的に加え、
"大覚寺統" の一代限りとされていた後醍醐天皇が、
「(その取決めに反して)自身の皇子に皇位を継承させる」というもう一つの目的がありました。
つまりその為には、
「"持明院統" の否定による皇統の統一」の実現と、それと同時に、
「"大覚寺統" の他の皇統をも凌ぐ必要」があったのです。
ということは、別皇統の天皇の "天意" …具体的には「理想としていた政治・国の在り方」も考慮しなければ、
フェアではありません。
詳しくはどこかで後述しますが、
手がかりは、"持明院統" の花園上皇が、甥である皇太子時代の光厳上皇に授けた『誡太子書』です。
室町幕府は本当に "天意に反する" 幕府だった?
いえいえ、仁政徳治主義を謳う『誡太子書』と、室町幕府が掲げた『建武式目』には、
実は驚くほど共通する精神が流れているのです。
「もう一人の将軍」
さて、先にも少し触れましたが、実は室町幕府は武家政権・鎌倉幕府の再開という側面が強かったんです。
つまり、鎌倉幕府の "否定" の元に始まったのではなく、むしろ "続き" といった感じです。
鎌倉幕府の基本法典『御成敗式目』を引き継ぎながら、行き過ぎてしまった北条得宗家による専制政治を修正し、
戦乱で乱れた世を立て直し、民のための政治を目指して『建武式目』が制定されました。
(※『建武式目』については…【『日本思想大系21 中世政治社会思想 上』(岩波書店)1980】
室町幕府の方針は、
「過去(古き良き時代)の善政に倣(なら)い、徳をもって国を治めよう」
というもので、
決して革新的なものではありませんが、
どこまでも正しさを求め、静かな中にも強い信念を感じさせる実直さは、
正に『武士の政権』と言うに相応しい、素晴らしいものだと思います。)
公平性や正義を最重要とし、"是非の基準" は富や権力ではなく『道理』にあるとする武家政権の高潔さは、
なんとも清々しいものですが、
でもこれ、尊氏一人の主導でなされたものではありません。
2歳違いで同母、でも性格は(一見)正反対の弟、足利直義(ただよし)に依るところが大きかったのです。
武士たちをまとめる『武家の棟梁』としての素質を持った尊氏と、
廉直(れんちょく)で誠実、その明晰な頭脳で政務を主導した直義、
正に "二人" によって生まれた幕府でした。 (※廉直…心が清く真っ直ぐで、行いが正しいこと)
足利直義については、兄の尊氏に比べて格段に知名度は劣りますが、
むしろこの幕府は、弟の直義がいなければ誕生し得なかったと言っても過言ではありません。
室町幕府誕生を象徴する最大のキーワード、それが ―――
「二人の将軍」
です。
(※もちろん、形式的には "征夷大将軍" に任命されたのは尊氏一人です。
ただし当時の史料では、制度上の "官職"(=征夷大将軍)としてだけでなく、
一般的な "武家の長" という意味でも「将軍」と言う言葉は用いられていて、
直義も「将軍」と呼ばれている場合があるので、
(…例えば、左武衛将軍、両将軍、将軍兄弟、など。 他に、両御所、両将、武将両殿下…とかも)
このサイトでもそれに従います。)
さてこのキーワード、
『太平記』に、「兄弟相並んで将軍となること、古今未だその例を聞かず」とあるように、
室町幕府を特徴付ける "最も特筆すべき点" であるはずなのですが……あんまり気にされてないよねw
しかもこれは、
単に「兄弟が力を合わせて開いた幕府」とか「兄を陰ながら支えた弟」を意味するのではなく、
間違いなく「二人でなければ…もしどちらかが欠けていたとしたら、実現しなかった幕府」と言う意味です。
こんな、正真正銘、本当の意味での「兄弟幕府」なんて世界的にも珍しいと思うので、
今後、この辺はさらに掘り下げていく予定ですが、
まあ2人の違いを簡単に説明すると、
考える前に勢いで天下導いちゃった兄の尊氏と、
国を憂い、頭使って幕府を創り上げ、荒れ果てた現状から天下を立て直した弟の直義、
といったところでしょうか。
尊氏は、武運の強さ、戦の上手さ、桁外れの人望で、時勢を掴むことにかけては天賦の才能がありますが、
直義は、類稀(たぐいまれ)な高い知性であるべき天下・理想の政道を明確に描き、
それを実現するに及んでは、どこまでも真面目で誠実だったのです。
ところで、普通、"歴史が動く時" ってのは、何かしら強力な権勢欲や覇権主義を抱いた者が、
一直線に支配者の座を目指す、みたいなイメージがありますが、
この時代を追っていて抱く印象は、
大将の二人に私欲が無い上に、
「果たしてこの展開、いったい誰が予想だにしただろうか?」という、"先の読めなさ" です。
まあそれ故、分かり難くて人気が無いのかも知れませんが、
始まりからして "たまたま" で、その後は偶然と成り行きで進む "とんでも展開ストーリー" というのも、
それはそれで面白いのです。
もともと、尊氏は積極的に新政権から離反する意図がなかったことは既に述べましたが、
それが "どうしてこうなった" 的な経緯(いきさつ)を、折角なのでもう少し詳しく解説してみます。
「東国へ駆ける」
建武2年(1335)6月、新政権の矛盾が限界に近づき出した頃、
京都で「公家によるクーデター計画」が発覚。(6月22日)
→ これは未遂に終わるが、その直後、東国で北条の残党がまさかの挙兵。(『中先代の乱』7月半ば)
→ この頃、鎌倉で東国の統治に当たっていた直義が、これまたまさかの大敗北。(7月22日)
北条軍に鎌倉を奪われ(7月25日)、三河国の矢矧まで敗走。(8月2日)
→ 東国の反乱鎮圧の為、尊氏が京都を出立。(8月2日)
→ 三河国の矢矧で直義と再会。 時を移さず反撃開始。(8月9日)
七度の合戦に連勝して進撃、一気に鎌倉を奪還。(8月19日)
この間わずか20日余り。
まず、事の始まりは、公家による反後醍醐天皇の動きだったんです。
この時点で、新政権開始から約2年。しかし社会の混乱は、もっと以前から始まっていました。
(※『二条河原の落書』が書かれたのは、この10か月前。)
この公家の西園寺公宗は、「国家転覆」の罪で他の共謀者と共に捕えられるのですが、
実は、西園寺家は鎌倉時代を通して執権北条一族と縁が深く、
その翌月、このクーデター未遂に呼応したのであろう北条残党による『中先代の乱』が東国で勃発した後、
結局、処刑されてしまいます。
ただし、この身分の公卿が処刑されることは異例中の異例であり、やや謎を残した一件でした。
もしかしたら…
このクーデター発覚の8か月前、
「帝位簒奪(さんだつ)」の罪(※)で捕えられた護良親王(後醍醐天皇の皇子)と同じように、
(真相は別の所にあるのだけれど)"新政権を脅かす恐れのある危険人物" という謀反人の疑いを着せられて、
排除された可能性も捨て切れないようですが…。
足利尊氏も、讒言によって暗殺のターゲットにされていたし、
後醍醐天皇の周辺の寵臣たち(貴族や僧侶や女官)の暗躍、内部での疑心暗鬼は相当なものだったようなので、
あるいは、裏に何らかの事情を隠し持った事件だったのかも知れません。
(※…表向きは「後醍醐天皇への謀反の陰謀」で処罰された護良親王(もりよし しんのう)ですが、
実際は尊氏の暗殺を命じられていたらしい。
…つまりどういう事かと言うと、
護良親王は、後醍醐天皇の皇子である上に、武将としても有力な存在で、何より独立心が強かった。
足利尊氏は、諸国の武士からの支持が高い上に、実は本来、後醍醐天皇からの信頼は厚かった。
天皇の近臣たちにとっては、この2人の存在は邪魔で仕方なかったでしょう…
上手いこと潰し合うように誘導しちゃえば…(手を汚さずに済みますね)
失敗しても…護良親王は「帝位簒奪」の罪を着せて投獄、尊氏は「逆賊」のレッテルを貼って討伐…
…ってとこでしょうか。 うーん、黒すぎるw)
(※ちなみに、護良親王については、新政権の讒臣たちに物申したいことが他にも山ほどありますが、
とりあえず今は我慢します。 (※讒臣(ざんしん)…讒言する臣)
ってか、護良親王も足利尊氏も "嵌められた側" だし、
足利直義に至っては(罪人とされた護良親王の)"事後処理を丸投げされた側" なのに、
『太平記』では、護良親王を、野心に駆られて非道を重ねる "極悪人" 、
尊氏を、讒言で親王を "嵌めた側" とした上に、
護良親王が『中先代の乱』という非常事態の中で処刑された後は、一転して "悲劇の皇子" に祭り上げて、
処刑を命じた(真面目なだけの)足利直義をここぞとばかりに非難するって、どんだけご都合主義なんだよ!!
…すまん、我慢できなかったw まあ、続きはまた別の機会に。)
(あーでもやっぱもう一言w
護良親王は「父帝への謀反」の罪で鎌倉に流罪となったのですが、
それを尊氏の思惑(つまり、尊氏が "宿敵" を自陣に引き渡すよう要求した)と見るのは無理があります。
そんな意見が自由に通る立場にあったなら、
そもそも尊氏が、佞臣の讒言で「後醍醐天皇から誤解される」なんて事は無かったはずです。
(その誤解を解く機会を与えられぬまま、逆臣とされてしまうのです。(※上記の「高僧の語録」より)
しかも尊氏は、それ(=讒言で逆臣となってしまった事)をずっと気に病み続けていた。)
それに、護良親王の勇猛果敢さを考えたら、
基本的に直義に甘い尊氏が、弟のいる鎌倉への流刑を望むとは非常に考えづらい。
(※この頃、尊氏は京都、直義は鎌倉にいた。)
つまり、普通に考えたら、「鎌倉への流罪」は新政権(の内部の近臣)の差配であり、
それはむしろ鎌倉の足利勢にとっては "重石" であった(近臣らは、それを狙っていたと言う事)、
それでも、護良親王の身を預かった直義は(責任を持って)真面目に監視下に置いていたのであり、
しかし結局、『中先代の乱』で北条の残党勢力に鎌倉を落とされてしまった際に、処刑に至った訳ですが、
ここで注意して欲しいのは、
護良親王は(少なくとも表向きは)"帝(ないし国家)への謀反人" として投獄されていた
という事です。
つまり、万が一護良親王が旧臣の手引きで逃げ延びて、再び軍勢を召集し始めるような事があったら、
それは、「後醍醐天皇の御身(もしくは国家)に危険が及ぶ」と言う事を意味するのです。(表向きには。)
後述するように、この時点での足利勢は "新政権の一員" として行動していますから、
この非常事態における処刑は、むしろ新政権側の者としては当然の「妥当な判断」であり、
已む無いものだったのです。
(おそらく、逃がしたら逃がしたで、新政権側は "直義の失態" として非難していたでしょうな。)
さらに、中世においては私闘の解決法として、
「加害者を、被害者側に引き渡して処分を委ねる」という事が認められていたので、
「尊氏暗殺未遂を起こした護良親王を、鎌倉に流した」
という事は、
新政権(の内部の近臣)にしてみたら、厄介払いすると共に、
実は、「後の処分はご自由に」と "暗に認めている" 事になる訳で、
また、表向きの「帝への謀反」という罪にしても、
(『太平記』の伝える護良親王の言葉にもあるように)これは本来「死罪」に相当します。
つまり、客観的に見ても、直義が責められる謂われは無いのです。
(…それでももちろん、
護良親王の死が悼むべきものである事に、変わりはありませんが。
のちに直義は、護良親王の十三回忌を鎌倉の東光寺(※現在は廃寺)で営み、冥福を祈っています。)
暗殺を命じられながら、それが(尊氏側に)露見したら(真相の口封じの為)「帝位簒奪の罪」を着せられ、
言い分も聞いてもらえず流刑となった護良親王の、『梅松論』に記された父帝への無念の言葉は、
恐らく事実に近いでしょう。
(※実は…、尊氏暗殺を密かに命じていたのは後醍醐天皇自身といわれ、
『梅松論』によると他に、新田義貞や楠木正成、名和長年も命を受けていたとされています。
ただし、その発端が近臣たちの讒言であっただろう事はほぼ確実と思われるし、
護良親王自身、(たぶん最も)打倒尊氏の意志が強かったようですが、
「武家(=尊氏)より、君(=父帝)がうらめしい」と呟いたという護良親王の心中を考え合わせると、
実に遣り切れないものがあります。)
…にも拘わらず『太平記』には、
「親王を処刑したなんて、やっぱり奴等(=尊氏たち)は反逆者だ!」
と、白々しく振舞う新政権内部の近臣の姿が描かれている、ってゆう。
……。
護良親王一人に罪を着せて流したのは、おめーらだろが!!!
しかもこれ、数ヶ月後になって「今知った」と言わんばかりに驚いて(という振りして)、
尊氏討伐の口実(決定打)にするんですよ。 嘘つけ!もっと前に知ってたはずだろ!!www
『太平記』によると、
『中先代の乱』(←この混乱時、護良親王が処刑された)の数ヶ月後、
京都の新政権内部では、鎌倉にいる尊氏の討伐を "迷って" いたのですが、
(↑実は、尊氏には「討伐に値する確実な罪が無かった」から。
それでもどうしても尊氏を亡き者にしたくて、口実を探していた。)
そこへなぜかタイミングよく(※建武2年(1335)11月頃)、
護良親王のお傍に仕えていた侍女が鎌倉から上京
→ 一部始終を報告 →「やっぱり尊氏は逆賊、討伐決定!」
という話になっているのですが―――
(※護良親王逝去…建武2年7月23日。 閏10月を含め、約4か月半ほどの空白。)
…って、なんだその数ヶ月の時間差は! なんだそのタイムリーさは!!
なんだその護良親王に対する手のひら返しは!!!
ってか、別のとこで、
「侍女は、護良親王を荼毘に付した後、すぐに髪を下ろして(=出家して)遺骨を持って上京した」
って書いてあるのは何なんだ!!
ってかそもそも、
尊氏には「非が無かった」事も、無実の尊氏を討伐するのが「道理に反する」という事も、
お前ら確実に自覚してたんじゃん!!
しかも尊氏にこじつけで着せた罪は、元はと言えば、もろお前らの罪だろがっっ!!
つまり、どういう事かというと…
逆臣だから討伐対象にしたんじゃなくて、
(なんか知らんけど)討伐決定して、後付けで "逆臣に仕立てた" って事じゃないか!!
何だそれは!もう!www怒w怒怒www
…さらに『太平記』には、
「鎌倉では直義が、護良親王を酷い環境に閉じ込め苦しめていた」とか記されていますが ―――
血も涙も無いのはおめーらだろぉぉーーー!!
だいたいなんだ! 都からの流刑人を禁固したのは、都の意向に忠実に従っただけの話じゃないか!!
「苦しめた」とか意味分からんだろが!!
直義が私怨でやった、みたいな言い方するなぁぁぁーーーっっ!!!
その上おまえ、
「直義は、護良親王の禁籠のための御所を設けて、武士に警固させていた」とか、
「光も届かない土牢に閉じ込めていた」とか、
書いてある事が矛盾してるだろがあぁぁぁーーー!!
ってか、当時の常識で考えたら、親王身分で土牢とか有り得んだろがぁぁぁーーーーー!!!
(※ちなみに、『梅松論』では「御所」となってる。当然です。)
自分らの悪巧みの結果を、直義に転嫁するなぁぁーーーーっっ!! 怒怒怒怒怒どどどどどど
はぁはぁ、
あーもう「あと一言」とか言いつつ、だいたい話してしまった、ふう、お茶でも飲んで落ち着こう。)
…という訳で、興奮に任せて話が先走り過ぎてしまいました。元に戻します。
(※ちなみに、『太平記』批判が過ぎてしまいましたが(ごめんw)、
確かに『太平記』は多くの潤色を伴っているものの、それ以上に真実を秘めた価値ある歴史書です。
潤色の下に真相が見え隠れするから、ついついムキになってしまう…という素晴らしい研究対象です。)
さて、上記の京都でのクーデター未遂と時を同じくして、
東国での北条残党の反乱、すなわち『中先代の乱』が勃発することになるのですが、
ここでもし直義軍が勝利を収めていたら、尊氏が京都を離れることはなかったでしょう。
しかし、事態は最悪の急展開を迎えたため、
急遽、尊氏は関東への下向を決意するのですが、しかし、後醍醐天皇に申し出るも許可が下りず、
勅許(天皇の許可)を得られぬまま出陣することになります。
『梅松論』に、「尊氏は、「私にあらず、天下の御為」と言って京都を立った」とあるように、
天下の非常事態においては正しい判断だったと言えますが、
しかし(元来、帝を慕う)尊氏にしては、意外なまでの強硬手段だったのは、
これはやはり、直義の身を案じたが故のレア展開だったと言えるでしょう。
(ちなみにこの時、尊氏は後醍醐天皇に総追捕使と征夷将軍の任命を求めますが、これも却下されます。
尊氏としては、東国の反乱鎮圧を優位に進め、戦功を挙げた家臣の忠節に恩賞で応える為の要求であり、
後醍醐天皇としては、武家政権復活を恐れての要求拒否だった訳ですが、
ただこの時点での尊氏は、事が済んだら京都に帰って来る気、わりと満々だったので、
「関東に着いたら、新政権から離脱しよう…しめしめ」と考えていた訳ではありません。)
さて、あっという間に鎌倉を取り返した尊氏、
後醍醐天皇の帰洛命令を受け、早速帰り支度を始めますがしかし、直義に止められます。
「ちょっと何考えてるんですか! 暗殺計画絶賛進行中の京都に帰るとか、正気ですか!
偶然が重なって、あれ?気付いたら鎌倉にいた。みたいなラッキー展開みすみす手放す気ですか!」(『梅松論』)
…って、そりゃ止めますよね。 帰ったらいつぬっ殺されるか分からんのだし。
という訳で、尊氏は直義と共に鎌倉に居座ることになりました。(もちろん、他に一門や家臣なども大勢います。)
ちなみに、この時京都に帰らなかった尊氏について、
「新政権に公然と反旗を翻した!」とかいう、
背後の事情をまるで無視した解釈が為されている事がありますが、ちょっとひど過ぎます。
殺されると分かっていれば帰りたくても帰れません、普通は。
これは結果的に「鎌倉の足利勢の想定外ピンチが、尊氏を暗殺の危機から救った」
というだけの事であって(※ちなみにこの "尊氏の強運"、この後一生続きますw)、
この時点ではもちろん、新政権への謀反の意志など無く、
後醍醐天皇公認のもと、鎌倉で東国の統治に当たりたいなぁ…くらいに考えていたと思います。
わりと、のん気に。
(※ "奥羽" (東北)を任されていた北畠親房・顕家父子と同様に、
"関東" は足利兄弟で、という構図です。
これまでは、関東にいたのは直義だけで、尊氏は京都にいました。
ところで、直義は一人鎌倉にいた1年半ほどの間、
後醍醐天皇の皇子成良親王(なりよし しんのう)を奉じて、関東統治に当たっていたのですが、
『中先代の乱』で敗走して三河国(※現在の愛知県東部)に落ち延びた際、
京都から尊氏が援軍に駆けつける以前に、直義は成良親王を京都に送り返します。
この直義の判断を、「鎌倉での武家政権樹立(=新政権離脱)の布石だ」と捉える向きもありますが、
しかし、それは少々当時の現状を見落とした理論だと思います。
鎌倉でボロ負けして遙々三河国まで逃げて来たような状況で、
一体、簡単に鎌倉が取り返せるだなんて、この時点で予測出来たでしょうか?
下手したら、鎌倉奪還どころか、関東の広範囲を巻き込んだ戦闘が何ヶ月も続きかねない、
そんな瀬戸際だった訳で、
どんな危険が待ち受けているかも知れぬ戦乱の巷に、
まだ幼い(数えで10歳)の成良親王を連れて行くなんて、現実的ではありません。
可能な選択肢は「三河国に残す」か「京都に送り届ける」のどちらかですが、
戦況が予測できない以上、親王の身の安全を第一に考えたら、
「京都」が最善の判断であった事に疑いの余地はないでしょう。
おそらくは、"鎌倉を落とされる" という失態を演じてしまった直義は、その責任感から、
「成良親王の御身だけは何としても」と考え、むしろ良かれと思って送還したのだと思います。
(つまり、この時点では当然、
足利軍はまだまだ "新政権の一員として" 戦っているのです。
ここは、非常に見落とされがち、かつ誤解されまくっている部分なので要注意です。
その裏付けとして、成良親王について、後でまた少し言及します↓)
つまり、当時の視点に留意することが大切で、
「鎌倉があっという間に取り戻せる」という結果は、後世の私たちにとっては周知の事実ですが、
当時の彼らは、壮絶な戦いを予想していたはずで、
「20日余りで奪還できる」なんて、常識的に考えて最も有り得ない未来だったと思われます。
そんな状況での「成良親王の京都への送還」を、「新政権離脱の布石」と解釈してしまうのは…
結果から逆算し過ぎです。
彼らの未来を知っている私たちと違って、彼らは自分たちの明日を知らないのです。
その時その場所に生きていた彼らの気持ちになってみれば、
そんなに簡単に明るい筋書きが描けるほど、未来は甘くなかっただろうことも、
そして、
「東から北条の残党に攻められながら、同時に西の新政権をも敵に回す」
という戦略に現実味が無いことも、少し考えれば分かる事だと思います。
それから同様に、
『中先代の乱』鎮圧後の尊氏の鎌倉居座りを以て「尊氏は新政権を裏切った!」と言われることがあるのは、
あまりに現状を無視した稚拙な誤解釈…というのは上述した通りですが、
これも彼らの置かれた立場を考えれば、容易に現実が見えて来ます。
そもそも、功績のあった尊氏を、
要らなくなったら(というか、人気が有り過ぎるから)一転して邪魔者として扱い、
密かに暗殺による排除計画を進めていたのは新政権側であって、
その危険から逃れたら「謀反人」呼ばわりとは、あまりにおかしな理論ですが、
そんな状況下にあってさえ、自ら好んで離反して朝敵となるなんて、デメリットでしかなかったのです。
確かに、当時の新政権と世上の惨憺たる現状を思えば、
武士である彼らは、
(鎌倉時代のように)やや京都の朝廷とは距離を置き、東国である程度(いやかなりw)自由にやりたいと、
そして、都の秩序とは違う "武家の信じる正義" に基づいた政道を追求していきたいと、
そう考えてはいただろうけど、
それは(少なくともこの時点では)、あくまで新政権の枠組みの中での話なのです。
(※これに関して、後でもう少し解説します↓)
当時の常識で考えれば、
わざわざ "自分たちから" 離反して新政権側の全勢力を敵に回すなんて戦略として愚か過ぎるし、
(一番現実的な戦略は…
そのままずるずる行って "武家による東国地方政権の既成事実化" といったとこでしょう)
そもそもこの時代、朝敵となることの不利を理解出来ない者など、いると考える方が困難です。
(少なくとも表向きには)京都の新政権の "一員" として、
「北畠親子が奥羽なら、俺らは鎌倉!」これが、賢い選択です。
―――ただし、
新政権の失敗がもう既に、"誰か" が立ち上がらねばならない所まで来ていたと言うこと、
そして、"新政権の方から" 正面切って切り離されたらお仕舞いだと言うこと、
それに(尊氏が)気付いていたかどうかは…分かりませんが。)
「さよなら、俺らの聖地鎌倉」
そんな訳で尊氏は、
今回の鎌倉奪還で奮闘した部下たちの戦功に対し、独自に恩賞を与えるなどしながら、
武家の聖地 "俺らの鎌倉" で、すっかりぬくぬくし始めます。
…ああ、このままみんなで、細々と秘密基地気分で暮らしていけたら最高だなぁ。
しかし、そうは問屋が卸さなかった。(やっぱりなw)
建武2年(1335)11月、尊氏、謀反の疑いをかけられ、
"尊氏討伐" の勅命を受けた新田義貞が、東国へ差し向けられる。(11月19日)
→ 足利軍第一陣、防戦に向かう。3日間の激戦の後、三河国の防衛線破られる。(11月25日~27日)
→ 直義軍、出陣。(12月2日) 駿河国の手越河原でこれまた敗北。(12月5日)
→ 尊氏、ようやく重い腰を上げる。(12月8日)
竹之下~伊豆の国府(足柄~三島付近)及び箱根で3日の激戦、大勝利。(12月11日~13日)
→ 伊豆の国府で合流した尊氏と直義(12月13日)、今後を相談。(12月14日)
勢い京都を目指す。(12月15日)
さて、後醍醐天皇には完全に切り離され、
水面下の「暗殺計画」は、顕然たる「討伐作戦」へと変貌を遂げます。
もうこの時点で、進むも地獄、退くも地獄。
この国で朝敵となることは、勝つか負けるか、正か不正かに関わらず "滅び" の道を約束されることに等しい。
立ち向かって滅びるか、それとも無抵抗のまま、護良親王や西園寺公宗と同じ道をたどるか…
どちらの道も "滅び" なら―――
そして彼らは、京都から下された追っ手新田義貞と戦う道を選ぶのです。 滅亡の闇に飛び込む覚悟を持って。
…の割りに、尊氏の出足が遅いようですが、何をしていたのかというと、
髻(もとどり)を切って、出家の準備始めてましたw …って、おい。
どうやら、本当に後醍醐天皇に叛くのが耐えられなかったらしく、
政務を直義に譲って引き篭もる気だったようです。
『梅松論』によると…
「ああやっぱりあの時、後醍醐天皇の仰せに従って帰洛しとけばよかったぁーーっっ
傍に仕えていたかったーーーっっ!! 一度だって、帝の御芳志を忘れた事なんてないのに…」
と大後悔。
まあでも、殺伐とした京都に、殺されに帰ろうとする兄を止めた弟の気持ちも分かってやれw
(ってか、あんだけ露骨な 讒言 & 君臣離間工作 & 暗殺攻撃 受けといて、まだ傍に居たいって…
お前はどんだけ素直でのん気で怖いもの知らずなんだよww)
まあ、こんなエピソードや、これまでの経緯からも容易に想像が付くように、
足利尊氏という人は、何を考えているのか(凡人には)さっぱり分かりません。
(一見、華麗なまでに行き当たりばったり…なのに何でも上手く行ってしまう、という、
意味不明なほどの "強運の持ち主" でもあります。)
この辺のゴタゴタ…
「新田義貞は(天下泰平の為に)誅伐すべしだと思いまーす!」と後醍醐天皇に奏上したり、
かと思いきや、寺に引き篭もったり…の支離滅裂さも、
従来、多くの歴史学者を悩ませて来た「尊氏七不思議」(←私が勝手に命名)の一つですが、
これに関しては素直に考えれば ―――
追い詰められてもう後が無い… でもどうしても後醍醐天皇に逆らいたくない…
だけどこのままじゃみんな死んじゃう… でもやっぱり天皇に弓引くなんて出来ない…
という、生まれついての武士である尊氏らしい責任感の表れと言えるでしょう。
(※従来、「尊氏は自ら好んで天皇に逆らった大逆臣だ!」
と思い込まれていた(ってか、そういう事にしたかった)為、
実際の "天皇を慕う尊氏の言動" を上手く説明することが出来ず、
都合悪いのでひたすらスルーで片付けられていた…っていう。
何それひどいw あんまりじゃないですかぁぁーー!!! )
…とは言えどう考えてもこの男、人生の半分を成り行きに任せています。
(※ところで、尊氏が「新田義貞誅伐」を後醍醐天皇に奏上??(※奏上…天子に申し上げること)
と、疑問に思われるでしょうが、
これはどういう事かと言うと…
新田義貞が後醍醐天皇から「尊氏討伐の勅命」を受けて、11月19日に出陣することになったのは、
これは "それ以前" から京都の新政権内部で、
新田義貞を始めとする近臣たちによる「尊氏討伐計画」が強引に推し進められていて、
後醍醐天皇に対し、「尊氏、謀反の気あり!」との讒言が繰り返されたことの結果な訳ですが、
(※尊氏討伐の背景が近臣たちの讒言であったことは、
上記の高僧の「語録」の他、『吉野御事事案』や『太平記』などでも共通した見解です)
それを事前に聞きつけた鎌倉の尊氏たちが、
「ちょwwおめーら、俺らを嵌め殺す気かコラ!!!」と、ぶっちり切れて、
「讒臣新田義貞、誅すべしだと思いまーーす!」との奏状を、後醍醐天皇に進上したのです。
(※奏状の内容を伝えるのは『太平記』のみですが(奏状が上げられた事自体は事実)、
やや大袈裟な修飾がなされている感じはするものの、概ね信じられる記述と思われます。)
この尊氏奏状の主旨は…
「讒言を以て乱を誘発しようとする新田義貞を誅伐したいので、早急に帝の勅許を御下しください。
(讒臣さえ除けば、全国を巻き込んだ大乱となる最悪の事態を、未然に防ぐ事が出来ます)
天下の泰平の為にどうかお願いします。」
…というもので、
一見すると「何でここへ来て後醍醐天皇に勅許を??」という感じで、
どう理解したらいいのか困ってしまう内容ですが、
しかしこれは、尊氏からすれば当然の君臣の礼であって、
この奏状の "真意" というのは…
「武家が帝に無断で軍を動かしたら天意に背く事になってしまうので勅許を求めた」
言い換えれば、
「武家の軍事行動は、勅命のもとで行われなければならない」
という "武家の原則" を、
尊氏が忠実に守ったという事を意味しているのです。
(※『中先代の乱』でも、(結果はどうあれ)尊氏はきちんと出陣に先立って勅許を求めています。)
この尊氏奏状が京都に届いたのは建武2年(1335)11月18日ですが、
実はこれに先立つ11月2日に、
直義が「打倒!新田義貞」の軍勢催促を、諸国の武士に向けて一斉に発しているので(おいw)、
時系列的には…
京都の 讒言攻撃 & 暗殺陰謀 の全容が鎌倉に伝わる
→ 直義激怒
→ 戦闘準備開始(11月2日)
→ 尊氏あわてる
→(無断で戦闘開始したら朝敵になりかねないので)新田義貞誅伐の勅許を後醍醐天皇に求める
…という順番だったと考えられます。
どうやら、(自身の危険に対して)のんきな尊氏よりも、
兄を亡き者にしようとする新田義貞にぶち切れたのは直義(および家臣たち)の方で、
尊氏はむしろ、自分の身より、鎌倉勢が朝敵となってしまう事を第一に危惧していたようです。
(※以上、カッコ内ここまで2016.2.7加筆修正)
それからもう一つ、この尊氏奏状から読み取れる重要な点は
鎌倉の尊氏たちは、この時点ではまだまだ当然、自分達も "新政権の一員" だと自覚していて、
その内部での争いだということをアピールしている、という点です。
(もちろん、現状かなり無理がありますw でもどうしても朝敵にはなりたくないのです。)
しかし、既に京都では「尊氏討伐」が議定し、
11月19日、新田義貞を大将とする官軍が関東に下されてしまいます。
この知らせを受けて、尊氏はまず、第一陣を三河国まで防戦待機に向かわせつつ、
奏状の返答を諦めずに待っていたと思われますが、
しかし、11月26日付けで尊氏は官爵(鎮守府将軍ほか色々)を削られてしまうどころか、
11月25~27日の戦闘で、新田軍に三河の防衛線を越えられてしまい、
主力軍出陣待った無しの状況に追い詰められた足利軍は結局、
"朝敵" として、"官軍" 新田義貞と戦う事を余儀なくされてしまうのです。
(※尊氏が出家遁世の意志を示したのは、
この三河の敗戦の一報が鎌倉に届いた頃、かつ12月2日の直義軍出陣前である事は間違いないと思われます。
勅許が叶わぬまま全面対決を迎えることになってしまった、
しかしそれでも "武家の原則" に忠実であろうとして、
直義の出陣に暗に許しを求める為に、出家遁世という行動で責任を取ろうとしたのでしょう。
―――2016.2.8追記 )
この辺りの事情(=尊氏たちの認識の微妙さ&意外さ)については、
一般に「武家と朝廷は "相容れない存在" である」と大きく誤解されているため、
この時の、鎌倉での尊氏たちの一連の行動も、
「武家政権を立ち上げる為に、"積極的に" 新政権から離反した」
と解されて来ましたが、実はそうではなく、
当時の武家社会の認識では…
「将軍は君(天子)を護り、国の乱を治むる職」
と『梅松論』にあるように、
「将軍とは、天子の秩序の一部である」
というのが大前提で、
「東国の地方政権の既成事実化にしろ、全国的な武家政権(=幕府)立ち上げにしろ、
その長である「将軍」となるには、天子の承認が必要不可欠」
だったのであり、
従って「自分達から朝廷を敵に回す」という戦略は、本来有り得ないのです。
しかし、彼らは既に、
(新田義貞らの讒言戦略によって)新政権側からきっぱり切り離されてしまった。
尊氏たちにとってこれは、想定外のどうすんの大ピンチ状態に他なりません。
おそらく、(今までなあなあで秘密基地気分の東国統治を続けて来た)彼らは、
この辺りでようやくw "なあなあ" を卒業し、
(こうなったらもう…)
「武家の信じる道理で天下政道を行い、世を正すしかない!」(=要するに、明確に幕府再開)
と、考え始めるに至ったと思われますが、
その為には、朝廷を "倒す" のではなく、戦に勝って、朝廷に "認めてもらう" 必要があったのです。
(※この後、最終的に討伐軍(=官軍)に勝利した足利軍は、新政権側と和睦を望みます。
天下の政道における主導権が、朝廷>武家(新政権)から、武家>朝廷(幕府政治)になるけど、
国家の秩序においては 天子>将軍 であることに変わりは無い、という事です。)
こうして見ると、
武家政権復活を恐れて「尊氏討伐」の先手を打った新政権の行動は、むしろ、
尊氏たちの退路を断って、「幕府再開」への道を一直線に走らせてしまった事になります。
眠らせとけばわりと猫なのに、叩き起こしてしまった獅子…だったと。
…ところで、
当時の記録に見える「将軍」とは、実は結構曖昧な言葉で、
漠然とした「武家の大将」というだけの意味なのか、それとも、
朝廷から任官を受けた(恒常的な役職としての)「征夷大将軍」「鎮守府将軍」「征東将軍」
…などの類を意味するのか、はたまた、
一時的な軍事作戦の長としての「総大将」(←元来の「将軍」の基本的な意味はこれです)を意味するのか、
判断が難しいところなのですが、
一つ確かな事は…
正式な場(発給文書等)で使用する「将軍」という称号は
「天子の同意を得ている」という意味を含む
という事です。
従って、それを称する事で、天子から委任された "何らかの権利"(統治権の類)がある事を、
世間に知らしめる効果もあるのです。
その証拠に、
建武2年(1335)11月26日、後醍醐天皇から官爵を削られて、大将尊氏が "無官" となり、
朝敵となってしまった足利軍は、
これまで、大将尊氏に対して用いていた「将軍」という呼称が使えなくなり(=天子の同意を失い)、
非常に苦しい戦いを強いられますが、
しかし(後述するように)翌建武3年(1336)2月15日、
持明院統の光厳上皇から(新田義貞与党人誅伐の)「院宣」を賜った(=天子の同意を得た)途端、
尊氏を(発給文書において)「将軍」と称し始め、
同時に(ややフライング気味にw)諸国の武士や寺社に統治権(※所領安堵の類)を及ぼし始めます。
(↑戦時における緊急の味方集めの為。
フライングな所に「背に腹は替えられねぇぇーー!!」というテンパった感じが表れている… )
もちろんこの時点では、何かしらの "正式な" 将軍職に任官した訳ではなく、
ここでいう「将軍」とは、
「「新田義貞与党人誅伐」の勅命を受けて軍事行動を遂行する一軍の大将」…つまり、
上記で言うところの、三番目の(元来の)「将軍」を意味する訳ですが、
尊氏を「将軍」と呼ぶことで、官軍となった事を内外に強力にアピールすると共に、
統治権の行使に正当性を与えているのです。
制度的に見れば、「ってか、何将軍のつもりだよ!!」という感じで有り得ないw話なのですが、
やつらに言わせれば、
「勅命の元に軍事行動起こしてんだから将軍は将軍なんだよ!! 何将軍とか知るかボケ!!!」
…といったところでしょう。
当時の彼らはわりと、名目より実質を優先したり、事後承諾的なことをする適当なところがあるので、
考察する方も柔軟な思考で挑まないと付いて行けないのです。 おめーら…
(※上記の「フライング統治権の行使」とは、有名な「元弘三年以来没収地返付令」のことで、
「建武政権期に没収された所領を返しちゃうよ! 涙目だったみんな集まれ~」
という大見得切った約束ですが、
この初見は、建武3年(1336)2月7日に発動されたもので、
これはちょうど、「院宣」を賜るため(在陣する兵庫から)京都の光厳上皇のもとに、
密使を遣わした頃(=2月3日~3日以内くらい)の "直後" に当たります。(※「院宣」獲得は2月15日)
つまり、完全に見切り発車です。 おめーら… )
という訳で、任官を伴わない「将軍」というと、
一見なんか、"朝廷軽視 & 武家の独自路線突っ走り" のように思われそうですが、
実は、反朝廷の意志表示ではなく、親朝廷の(強引なまでの)"超絶アピール" だという事と、
それからこの(半ば勝手なw)行為がもし、世間で総スカンを食らったというのなら、
(後世から逆賊と)非難されても仕方ありませんが、
しかし、現実問題として、その後の足利軍は諸国の武士を盛大に味方に付けて行きます。
これは取りも直さず、
「当時の民意は「将軍」を待ち望んでいた」
という事に他なりません。
…以上、後半は少々小難しい話なので、今は聞き流してもらって構わないのですが、
この時の「尊氏たちの本意」や、「室町幕府の本質」にも関わる割と重要な問題なので、
いずれ改めて、文献等を提示しながら解説する予定です。 ―――2014.12.29追記 )
(※2016.2.8追記。 一応参考文献の提示のみしておきます。
【家永遵嗣『室町幕府の成立』(『学習院大学文学部研究年報』第54号 2007 2008年3月)】
【桃崎有一朗『初期室町幕府の執政と「武家探題」鎌倉殿の成立
―「将軍」尊氏・「執権」直義・「武家探題」義詮 ―』(『古文書研究』第68号 2010年1月)】
…の p.46-47、特に p.61-63 の一覧表。
卓越した着眼点で様々な問題を提起する示唆に富む論文です。
ただ、上述の私の論旨は、当論文の結論とは異なります、すみません。 …まあ、詳しくはまたいずれ。)
さて、またまた話が先走ってしまいました、戻します。
髻まで切って、出家秒読み段階に入った尊氏ですが、
しかしではなぜ、また一転して出陣に踏み切ったのかというと、それは―――
直義が大敗北したから。
「直義が死んじゃったら、俺生きてても意味ねぇぇーーーーー!!」 (『梅松論』)
そして一方で、
「で、でも、天皇に弓を引くつもりはこれっぽっちも無いんだからね!
あくまで敵は新田義貞なんだからねっ!」
と、誰に向かって念を押しているのか分かりませんが、とにかく満を持して立ち上がり、
一途、直義の待つ箱根へ向かいます。
(ちなみに、『太平記』によるとこの時、
尊氏の(髻切っちゃった)ダサ…じゃなかった、異様な髪型を隠す為、
鎌倉中の軍勢が、
「うおぉぉーーーーならば俺らも!!」と、揃いも揃って髻をスッパリ切ったという。
世に言う「一束切り」(いっそくぎり)である。
(※「一束切り」とは、髻を、根本から一束(=こぶし一握り)分の長さを残して切ること。
参考画像は…これまで足利尊氏像だとされて来た、
あの有名な「騎馬武者像」(※実は、この時「一束切り」をした家臣の一人)をどうぞ。)
てゆうか、大将の出家撤回宣言に歓喜して奮い立ってしまったのだろうけど…
これから出陣という時に集団で出家コスプレって。 おめーら… )
さて、直義救援に向かった尊氏ですが、直義の布陣する箱根峠には向かわず、
12月10日の夜、それより北の足柄峠にこっそり到着し、夜が明けるのを待ちます。
これは別に、あまりに髪型がダサ過ぎて、直義に会うのが恥ずかしかった…訳ではなくて、
「(当然)箱根で合流して攻めて来るだろう」と予測している敵の裏をかいて、
北へ迂回し足柄峠を使って夜のうちに山を越え、
箱根山の西側に対峙する新田義貞軍を、北から奇襲する作戦だったからです。
古来、名大将には名軍師が付きものですが、
足利尊氏という人は「大将と軍師を兼ね備えている」という、わりとマジで有り得ないスペックの人物なのですw
(※普段の人生では、成り行きの3歩後ろを歩いているのに、
戦の時だけは、驚異的な先読みで誰よりも未来に生きる男、尊氏。)
12月11日~13日にかけて、竹之下 → 佐野 → 伊豆の国府と、息もつかせぬ突撃南下作戦で、
これまたあっという間に形勢逆転、
箱根での直義軍の奮闘(やや苦戦w)と相俟って、新田義貞軍に圧勝した尊氏は、
伊豆の国府(※現在の静岡県三島神社付近)で直義と合流し、
「で、次どうする? 鎌倉帰る? それともこのまま京都までとっ込んじゃう??」
と、みんなで相談の結果(※)、
「ぬおーー!! ここまで来たらもう、この成り行きウェーブに乗ってしまえぇぇーーーっっ!!」
ってことで、西への遥かなる旅が始まったのでした。
(※…『梅松論』によると、12月13日に合流した尊氏軍と直義軍は、
翌12月14日、今後の彼らの運命を決定付ける、重大な軍議を開きます。
「これより、尊氏直義の両将は、鎌倉に帰って関東を沙汰すべきか」
「しかし、たとえ関東を全うしたとしても、東海道や京都の合戦は(避けられない)重大事だ」
「ならば、両将一手に出立するに勝るものは無い!」
ここでまず重要な点は…
この時点では、彼らは鎌倉に帰って "東国統治の続き" に戻ろうとも考えていた、という事です。
おそらく、後醍醐天皇の誤解を解き、朝敵撤回をしてもらえるつもりだったのかとw
(ここまではやはり、
あくまで "敵は讒臣新田義貞" であって、朝敵じゃないもん!なのです。
――― いや、だから無理があるだろ、ムリムリだろ…という突っ込みはさて置き、
彼らが鎌倉を立ったのは、新政権から "離反したから" なのではなくて、
新政権から切り離されて "戦う以外の道が無かった"、というのが正確なところでしょう。)
しかし、彼らは鎌倉に戻らず、西を目指す決意をします。
私は、尊氏たちが「明確に(鎌倉幕府と同等の)武家政権再開を心に決めた」のは、
この時点だと思っています。
遂に後ろを振り向く事をやめ、彼らの未来が大きく塗り替えられた瞬間が、
この、『竹之下・箱根の合戦』だったのです。)
…ってゆーかそれにしても、
なんて行き当たりばったりなんでしょうか、適当すぎる。
しかも、そんなに強いんなら初めからやる気出せよ、とか言いたくなりますが、
ここはむしろ、直義の "戦弱さ" が気になってしょうがないですねw
(※この、12月5日の駿河国手越河原での敗北は、極めて際どいもので、
一時、「大将直義、ここにて討死!」の "最期の決戦" を予定したらしいが、
家臣の意見が割れて、箱根まで退却する事になったそうだ。(『難太平記』))
やる気も、人望も、大将としての気概や勇気も、十分に備えているとは思うのですが、
やはり廉直すぎると一直線に突き進み過ぎてしまうのですかね、野生の勘で動いているっぽい兄と違って。
ただ、結果的にそれが尊氏を動かしたことを考えると、
直義が戦に弱かったから歴史が動いた、と言っても過言ではあるまい。 (…すみません、過言です。)
(ちなみに『太平記』には、この時、
「尊氏の出家を阻止して出陣を促す為、駿河国で敗北した直義が一度鎌倉に戻り、
「たとえ隠遁しても尊氏たちを許さない」との後醍醐天皇の「偽綸旨」を十数通も偽造し、
それを出家準備中の尊氏に見せて、嘘泣きしながら出陣を訴えた」
…という、かなりうさん臭い話がありますが、
(※綸旨(りんじ)…天皇の意を奉じて発する文書)
しかし、『梅松論』や軍忠状の記載と比較して、
直義が「鎌倉に一旦戻った」と考えるのは、日数的に余りに無理があるし、
戦況的にも、目前に迫る新田義貞軍の進攻を食い止めるので手一杯の敗軍の直義が、
実質たった2日でそんな余裕ある謀略を遂行した、とは到底考えらず、非現実的です。
(※実際は、12月5日の終日の合戦で大敗し、
駿河国から(伊豆国と相模国の境の)箱根峠まで後退して、そこですっと引き篭もっていたw)
何より、大将自ら前線に出て戦い、後が無いとなれば討死も辞さない性格の直義にしては、
綸旨の偽造なんて作戦内容はせこ過ぎます。
(…ただし正確には、偽綸旨の発案自体は家臣の一人によるもので、直義はその策に従っただけ、
という話ではありますが。 ―――2016.2.20追記 )
(※ちなみに、内容の信憑性では基本的に、
手記『難太平記』 > 軍記『梅松論』 > 軍記『太平記』です。 詳しくは後述↓)
そもそも当時、
『二条河原の落書』にも歌われているように、
「謀綸旨」(にせりんじ)という、"土地の権利関係" で横行した困った流行(社会問題)があって、
『太平記』の話は、そこからヒントを得た物語上の潤色だと思われます。
(尊氏が、出家から一転出陣に踏み切った理由を "無理矢理説明する為" に。)
他の数々の史料(後々紹介します)にも表われている様に、
本当に直義は、間違った事が大嫌いな人物なのです。)
「西へ」
ともあれ、足利軍は一路、京都を目指すことになるのですが、
上述のように、彼らは九州まで到達してしまいます。
これは別に、あんまり助走つけたもんだから、勢い余って九州までつんのめってしまった…訳ではなくて、
京都で一旦ボロ負けwしたからです。
建武3年(1336)正月、伊豆から攻め上がった足利軍、一旦入京に成功するも(正月11日)、
カウンターパンチ食らって敗退。 丹波に逃げる。(正月27日~30日)
→ 兵庫に移動。(2月3日)
西国からの援軍を得て、再度京都に攻め上ろうとした矢先、
攻め込んで来た官軍にボコボコにされ(2月10~11日)、コテンパン九州堕ち。(2月12日夕刻~)
→ 船に揺られて、播磨国の室津に到着。(2月13日夜明け前)
ここで軍議を開き、今後の防衛戦略を立てる。(『室津の軍議』2月13日~14日)
→ 船旅再開、備後国の鞆に到着したところで、京都から光厳上皇の「院宣」と錦の御旗を賜り、
にわかにボーナスステージに突入する。(2月15日)
→ ようやく長門国の赤間関に到着。(2月20日)
九州(筑前国の芦屋津)に渡り(2月29日~30日)、博多でひと合戦のち大勝利。(3月2日)
1か月休んで、京都を目指して東上開始。(4月3日)
→ 『湊川の戦い』で、新田義貞と楠木正成を破り(5月25日)、
遂に入京を果たす。
(直義入京、5月29日
尊氏入京、光厳上皇と豊仁親王(のちの光明天皇)を奉じて、6月14日)
京都を敗退した足利軍は、丹波を経て兵庫(※現在の神戸市中心部の沿岸地域)まで退き(2月3日)、
次の一手を模索します。
摂津国の摩耶での籠城戦という選択肢もあったのですが、
しかし、 ある部下曰く、
「もし、ここで籠城なんてしたら、
「なんか尊氏とかゆう奴、ボロ負けして引き篭もってるらしいぜ、プゲラwww」
とかいう恥ずかしいうわさが立って、全国の武士にそっぽ向かれます!
ここは何が何でも、かっこつけるべきです!」 (『梅松論』)
なるほど…という訳で、西国から海路で駆けつけた援軍(大内&厚東勢)に勢いを得て、
京都再突撃でかっこつけてみようとした足利軍ですが、
しかし―――
兵庫に到着した時点で彼らは… わりと凹んでいたw
これまでの連勝記録が嘘のように、合戦が上手く行かない。
戦術も戦略も無双に近い足利軍が、ここへ来て大苦戦を重ねるその敗因は―――
すべて、彼らが背負った「朝敵」の汚名にある。
ああ、錦の御旗の輝きが恋しい…
と(たぶんそんな感じで)、
戦闘の迅速さで天下にその名を轟(とどろ)かせる足利軍にしては珍しく、
兵庫に移動してから3日間ほどぐすぐすして(『太平記』)、
うだうだと戦略をこねくり回しては、あーだこーだ(※)していると…
(※…あーだこーだの内訳
諸国の味方への「出動要請」(2月4日、5日)とか、
上記の「脱☆朝敵! 光厳上皇の "院宣" 獲得作戦」(で、密使を京都へ)とか、
軍勢確保の為の「フライング統治権発動」(=「元弘三年以来没収地返付令」)(2月7日、8日)とか)
しかしなんと、
追い討ちをかけて来た官軍の楠木正成と新田義貞に、その場で再び打ち負かされ(2月10日~11日)、
どっちにしろ(かなり)かっこ悪いことになってしまった、
という悲劇的な展開を迎えてしまいます。 なんてこった。
こうなったら…
意を決して最後の手段に出るしかない!!
「お、おう。今日のところはこの辺で勘弁してやるぜ。
あっそうだ、ちょっと九州行ってくるっ」 (=要するに、逃走)
ということで、ボロ負け瀕死の足利軍は、
さっき来たばっかの西国の味方の船に乗り、
人馬を休ませ軍備を整え、態勢を立て直すべく、
再起を誓って、海路で更なる西へと旅立ったのでした。(2月12日夕刻)
(※ちなみに、この兵庫での再敗北で直義は、
切腹の着到(=切腹名簿)を付け(『難太平記』)、
今日を限りと決死の徹底抗戦に出ようとしていたのですが、
尊氏が何とか説得して九州に退く事になったとか。
直義「都(みやこ)に攻め上りて命捨つべし!!」(『梅松論』)
尊氏「ちょwww落ち着いて! 逃げるよ!一旦逃げるから、直義ちゃん? ねっ、聞いてる??」 )
…ってか、無計画の割りに、やる事のスケールが大き過ぎますね。
京都通り越して九州とか、まるでイミフ展開ですが(イミフ=意味不明)、
しかし、この九州堕ちの途次、
備後国の鞆にて、足利軍は遂にその命運を覆す瞬間を迎えます。
すなわち、上記の密使がミッションに成功して、
持明院統の光厳上皇から賜った「院宣」(いんぜん)と錦の御旗をもたらし、
彼らは晴れて朝敵返上を果たすのです。
(※院宣…上皇の意を奉じた文書)
(室町幕府は「天意に反した幕府だ!」なんてのは実は誤解でして、
持明院統(つまり北朝)の天皇には、こうしてちゃんと認められているのです。
後醍醐天皇(つまり南朝)を尊重する余り、
相対的に持明院統(北朝)の天皇が軽視されている現状は、やはり残念だと思います。(ってか、失礼だよねw)
しかもあれですよ、持明院統には…
超ハイクオリティな頭脳&思考をお持ちの壮大な帝――― 花園天皇がいらっしゃるのです!
(※花園天皇は上述のように、甥である皇太子時代の光厳上皇に『誡太子書』を授けた方です。)
この時代の "桁外れ人物" の断トツ筆頭ですよ、花園天皇は。
マジで、言ってること…失礼、おっしゃってること超かっこいいからw
でもみんな、あんまり知らないでしょ? この先、ちょくちょく言及させて頂きますから、お楽しみに!)
…という訳で、
足利軍、無敵モードでボーナスステージに突入する!!
早速、九州の味方大友千代松(氏泰)に宛てた書状には
「新院(=光厳上皇)の御気色(=ご意向)によりて、御辺を相憑て鎮西に発向候也…(以下略)
二月十五日 尊氏 」
つまり、「天子様の承認をゲットした官軍の僕らが、YOUを頼って九州に参上しちゃうぞ☆☆」
という、ついさっきまで蒼ざめた瀕死の逃亡軍だったとはとても思えない浮かれっぷりで、
官軍となったことを、これでもかと方々にアピールし出す彼ら。
『梅松論』に、
(院宣を賜って)人々は勇み立ち
「これでもう朝敵とは言わせないぜ!! オラおめーら、錦の御旗を振りかざせっっ!!」
と、国々の大将(※)に通達した。
とあるように、実際、2月15日を境に、
(上述の如く)足利方では書状において、彼らの大将尊氏を「将軍」または「将軍家」と呼び始めるのです。
(※…これ以前、播磨国の室津において、彼らは軍議を開き(2月13日~14日)、
京都からの官軍の追撃を防ぐ為、山陽・四国地方の各国に「大将」と「守護」を設置し、防衛に当たらせます。
これがいわゆる『室津の軍議』あるいは『室泊(むろどまり)の軍議』と呼ばれるもので、
その後の室町幕府守護体制のβ版と目されていますが、
彼らはその、つまり… 2月14日までは、相当ビビってたんだよ!!)
(※ちなみに、光厳上皇の「院宣」を拝受した日は定かではありませんが、
上記の大友千代松宛文書から、2月15日以前である事、
かつ、備後国の鞆に到着した時だった事、
そして、少なくとも2月14日の朝までは播磨国の室津に逗留していて、
室津~鞆は半日強~1日弱の行程(※この7割ほどの距離の兵庫~室津が約10時間)である事から、
院宣を手にしたのは2月15日だろうと推測しました。
また、『梅松論』では、
2月11日の兵庫での合戦敗北後に、赤松円心(則村)が「院宣」獲得を勧めた、とありますが、
約4日間で、「院宣の交渉」と「兵庫→京都→鞆の移動」が可能であるとは思えないので、
これに関しては、兵庫での「合戦前の計画」だとする『太平記』の記述に、軍配が上がります。
ただし、発案者については、尊氏とする『太平記』ではなく、
赤松円心とする『梅松論』(※こちらの方が、足利軍の内部事情に詳しい)が正しいように思います。
おそらく『梅松論』の院宣提案の話は、
本来、2月3日(兵庫での合戦前)に赤松円心が「摩耶城への退避」を勧めた時に同時に進言したものだったのを、
間違って、2月11日(兵庫での敗北後)に、同じく赤松円心が「西国での態勢立て直し」を勧めた時の話として、
記してしまっただけだと思われます。)
さて、鎌倉を飛び出したあの日には、京都ですっ転んで九州までダイブすることになろうとは、
夢にも思っていなかった訳ですが、
このとき始まった持明院統の天皇との関係は、室町時代を通しての親密な公武関係を築く一歩となり、
その皇統は、現在まで繋がる運命的なものとなります。
まあしかし、ボーナスステージって言っても、
やはり先の知れぬ旅であることに変わりはありませんでした。(『梅松論』)
船の援軍が来るくらいですから、西国にも味方はいるものの、未だ訪れたことのない遠国、
不安に揺れる夜を、船の上でいくつ数えたことでしょうか。
九州では、新政権方との戦いで苦戦する味方の少弐(しょうに)方に加勢すべく乗り込んでみれば、
数十倍はいるかと思われる敵方。
圧倒的な兵力の差に尊氏は、
「…詰んだ。俺ら詰んだ。
ぬおーーーっっ俺ら詰んでんじゃんもう!! かくなる上は…切腹でござるっ!(てへ)」
「待って待って!ww 戦ってみないと分からんでしょうが!
それではちょっと行って参ります。 死ぬ気でGO!!」
と、微塵も躊躇せずとっ込む直義に味方の士気は上がり、神展開の大勝利!!
(おお! 直義が勝ったw
まあ実は、なんだかんだ言って直義も強いんです。
ただ、「武士たる者、命を顧みず全力でとっ込むべし!」というタイプだから、窮地に陥ることも多い。
一方尊氏は…
戦略を立てる → 勝つ予定が決まる → 命は惜しくないので矢が飛び交う前線にも出る →
でももう予定入ってるので負けない → 命は惜しんでないのに死ねない → 勝っちゃう… ってタイプw
ちなみに、実際に負けた時すら、基本的には勝ったつもりでいる。
マジ笑かしてくれる人ww どうなってんだよ尊氏ってwww )
(※ところで、この『多々良浜の戦い』(※多々良浜…博多の少し北)について、
『梅松論』と『太平記』では、
「合戦の経過」(=直義の出陣&奇蹟的大勝利)に関しては、だいたい同様の記述となっているものの、
「尊氏の言動」については、少々見解が異なります。
(※『梅松論』では、尊氏は戦略として "敢えて" 出陣をせずに後方待機、となっていますが、
ここでは仮に、『太平記』の "怯む尊氏" の方を採用しました。 理由…おもろいからw)
いずれにしても、この時の尊氏は、
普段の恐怖知らずな尊氏と比べて、かなり様子がおかしかったのではないか?―――
…と、私は常々思っていたのですが、
どうやらそこには、誰にも言えない "ある大きな理由" があったようです。
まあ、詳しくはまた別の場所で。 ―――2015.5.2補足)
さて、奇蹟的な勝利で合戦を終えた…だけでなく、
数え切れない降参人を、持ち前の寛容さで大量に味方に迎えて、
ちょっと一休みの春。
「どうする? 兵粮(ひょうろう。戦時の兵士の食糧)のこともあるし、
このまま収穫の秋までぬくぬくしちゃう?
(九州のコメうまいかなぁ。あーめし食いてぇなぁ…)」 (『梅松論』※ただし括弧内は私の妄想)
とそこへ、播磨国(※現在の兵庫県南西部)を守る味方がきゅうきゅうという知らせが入ったため、
急遽、九州のコメに別れを告げて、2か月前リベンジを誓った京都へ、最後の船出が始まりました。
涙目で堕ちていった往路とは打って変わって、膨れ上がった軍勢を率い、
途中、"海路" の尊氏軍と "陸路" の直義軍に分かれて、勇む復路の行く手には、
新政権方の強敵、新田義貞と楠木正成の軍勢が待ち構える運命の大決戦、『湊川の戦い』が、
その幕開けを待っていたのでした。 (※湊川…現在の神戸市中心部あたり)
"時" を読み、諸国の武士の "勢" を味方につけ、"天命" の導くところ、「勝利」は足利軍に訪れましたが、
しかし、この時代の特筆すべき(困った?)点は…敵方も魅力的過ぎる、というところです。
武略に長けた楠木正成は、
諸国の武士の志が新政権側から離れ、尊氏直義の両将に靡(なび)いていることをいち早く察知し、
人心の行方から戦の勝敗を悟って、
後醍醐天皇に、(新政権内の讒臣を誅伐して)尊氏と和睦するよう、
涙ながらに忠言を申し上げたのですが聞き入れられず、
こうなってはもう、最前にて討死あるのみ…と、死を決意してこの "最期の戦" に挑み、そして散って行きました。
その深い思慮はどんな賢才武略の勇士にも勝ると、敵味方に惜しまれたと言います。(『梅松論』)
(『太平記』によると、
この『湊川の戦い』で、直義は楠木正成に追い詰められて絶体絶命のピンチに陥りますが、
それを聞きつけた尊氏の「直義討たすな!!」との一声で六千騎の援軍が駆けつけ、一気に逆転したらしい。
…ああ、また、直義の "戦弱さ" が歴史を動かしてしまった。)
「夢を見ていたんだ、きっと…」
さて、先の京都敗退から4か月、足利軍の「凱旋」は同時に、「新しい時代の始まり」となりました。
建武3年(1336)8月15日、
持明院統の豊仁親王(のちの光明天皇)の践祚(せんそ。皇嗣が皇位を継承すること)。
→ 大覚寺統の後醍醐天皇と和睦。(11月2日)
→ 幕府の基本方針を記した『建武式目』を制定。武家政権の再開をここに示す。(11月7日)
足利軍の入京後も、洛中での市街戦は断続的に続いたものの、大筋の情勢が覆ることはなく、
豊仁親王(光厳上皇の弟で、のちの光明天皇)の践祚、後醍醐天皇との和睦、
そして和睦の証として、後醍醐天皇の皇子である成良親王が皇太子に立てられ(11月14日)、
『建武式目』を掲げた "二人の将軍" の幕府が、その一歩を踏み出したのでした。
(※先の『中先代の乱』で、三河国から京都に送還された成良親王が、
この時、後醍醐天皇と武家との "和睦の象徴" になり得たと言う事実からも、
あの送還には、「成良親王の切捨て」だとか「後醍醐天皇との決別」という、
否定的な意図は無かった事が分かります。
それから、
「持明院統(北朝)の天皇は、逆臣足利尊氏に奉じられたニセの天皇だ! 北朝は "偽朝" だ!」
という、
(何百年も後の)近世・近代になって "突如" 現れた極端な史観がありますが、
武家政権が推戴したのは、持明院統(北朝)だけではありません。
大覚寺統(南朝)の皇子を皇太子に立てている、という紛れもない事実があり、
何より持明院統(北朝)も武家政権も、「後醍醐天皇(南朝)との和平」を願い続けていたのです。
天下泰平を祈り続けた当時の人々を、なぜここまで貶めなければならないのか、
理解出来ません。)
足利尊氏が、突然の東国での反乱(『中先代の乱』)の鎮圧の為に京都を立ってから、
最後の入京を果たすまでの約1年間(11か月半)、
長い旅の途中、慣れない土地で迎えた夜は心許なく、
しかし夜明けはその都度、彼らに希望を呼び起こしたでしょう。
勝敗の読めぬ戦いが、予想できない展開で進み、闇の先を天に任せるしかない日々の中で、
それでも、「信じ続ければ、未来は必ず応えてくれる」という事を教えてくれる真実の歴史物語というのは、
そう無いんじゃないかと思います。
そしてまた、鎌倉幕府終焉から室町幕府誕生までの、
明日がどちらに流れるかも分からない混沌としたこの時代にあって、
この "二人の将軍" のもとに諸国の武士が結集することになったのは、
清和源氏の血を引く足利家の "貴種性"(血筋の高さ)も然る事ながら、
二人の大将としての器―――義に篤く私曲を交えぬその姿勢が、
忠節を尽くすに値する『武家の棟梁』と認められたから、と言っていいでしょう。
(※私曲(しきょく)…自己の利益だけをはかって、不正で邪(よこしまな)こと。)
足利尊氏・直義二人の人柄が、同時代の人々から非常に高く評価されていたことは、
当時の諸記録に書き残されていますが(そのうち紹介します)、
特に弟の直義は、正しい政道への意欲が本当に強く、家の為とか武家の為といった次元を遥かに超えて、
民衆の啓蒙・教化まで視野に入れた、"天下の為" の政道を志していたのです。
(この、"真夜中に夜明けを見出す" が如く、未だ見ぬ "輝かしい理想の天下" への希求心は、
とある高僧…すなわち、夢窓疎石(むそうそせき)との対話を記した『夢中問答集』という書に現れていますが、
まあ、詳しくはまたどこかで。
…ちなみに、
「直義は、天皇親政の新政権を倒して、武家に主権を取り戻す事を "目的" としていた」
みたいな解釈をされることがありますが、
この時期の歴史を「天皇 vs 武家 の政権の奪い合い」といった表層的な視点で見ていては、
尊氏・直義の行動原理は理解出来ません。
そもそも、 彼らにしてみれば、本来忠功のあった尊氏が朝敵とされたのは、
「先皇(=後醍醐天皇)の佞臣等の讒口によって、
叡慮(=後醍醐天皇のお考え)にいささか異変(心変わり)があった」(『吉野御事書案』)
ための誤解だったのであり、
建武2年(1335)末に鎌倉を立ち、『竹之下・箱根の合戦』を経て上洛を決めたその本意は、
「(新政権内の)賊臣を退かんが為に、義兵を起こさるる」(『吉野御事事案』)
すなわち、
間違った者を除き政道を正す為の戦いだった訳で、
『夢中問答集』にも、この時の行動が「義兵」と記されているように、
直義が一番に重視していたのは、
「政道が正しいか正しくないか」(人々の求める政治であるかどうか)
だったのであり、
その担い手が「誰であるか」では無いのです。
(新政権を倒し武家で権力を独占することが "目的" だったのなら、和睦など望むはずがありません。
直義の目的は「政道を正す事」であって、「政権を握る事」は単なる "手段" に過ぎないのです。
もし仮に、新政権が正しく機能し、それが民意に適ったものだったのなら、
尊氏は京都、直義は鎌倉にいたまま、時代は流れていたでしょう。)
当時の典型的な武士というものは、「道義的な正しさ」を唯一にして最高の規範としていたのであって、
自己の野心とか覇権などと言った個人的な欲で、動いていた訳ではないのです。)
ちなみに、兄の尊氏はというと…
建武3年(1336)8月17日、「よしっ、これからが本当の始まりだぜ!」という、正にその時、
京都の清水寺に、
「この世は夢の如くに候…」で始まる願文(がんもん。神仏への願いを記した文)を納め、
今生の果報(現世の幸せ)のすべてに代えて、
後生(来世)を、そして直義が安穏に守られることを心から祈り、
"遁世宣言" してましたw …って、おい。
まあ、この隠居は実現しませんでしたが、
尊氏という人は、めっちゃ強いし、人も好いけど、ハチャメチャであることは間違いないですね。
(弟に政務を譲った尊氏は、ある日直義に向かって、
「国を治める職に就いたからには、重々しく振舞わなくてはいかんぞ。
遊興に時間を費やすとか以ての外だぞ。
花や紅葉くらいは構わんが、(芸能の)見物とかほどほどにな。
…まあ、つまりあれだ。
俺は軽々しく振舞って諸侍に慕われ、人々に親しまれ、朝家(天皇)をお守りしたいのだ。
だからと言ってはなんだか、お前は重く行けよ、いいな?」 (『梅松論』)
…って、おいw
でも、本当に遊ばず、政務に一直線に励んだ直義でありました。 泣けるw
ちなみに、尊氏本人は田楽(芸能)大好き。 おい!!)
まあ、この一年の天下の流れが、
尊氏にとって(仏教的な意味での)夢のようなものであったのは、なんとなく分かりますが、
しかし、現実の世界の物語は、この先も続いていきます。
そしてそれは、あまり… 悲しいことに、喜びと安らぎに満ちたものではありませんでした。
「たどり着いた場所」
世の中が落ち着くべきところに落ち着くには、まだまだ長い時間と多くの犠牲が必要だったのです。
建武3年(1336)12月21日、その前月に和睦したはずの後醍醐天皇が、
大和国(※現在の奈良県)の吉野へと密かに逃れたことで、
朝廷は、吉野の南朝(後醍醐天皇)と、京都の北朝(持明院統)に分裂し、
全国を巻き込んだ『南北朝の動乱』へと発展していきます。
ただそれでも、建武3年(1336)幕府発足からの十数年間は確かに、
鎌倉幕府崩壊以来の秩序を失った政道の立て直し、戦乱で失われた命への弔い、都の再建…と、
乱れた世に泰平をもたらそうと、彼らが必死で重ねた努力と共に、
幕府は、着実に新しい時代を築き上げ、
人々は乱世の終わりを祝い、穏やかな都で始まった未来に安堵する事が出来たのですが、
しかし―――
秩序と道義を重んじ一心に正しき世を目指す直義の、その情熱のすべてを注いだ世界を、
それぞれの私的思惑を絡み合わせ、打壊すべく結託した一部勢力の強硬手段が、
突然に泰平を破ってから2年と半年後、
尊氏・直義兄弟の悲しい結末が、その訪れを待っていたのです。 (『観応の擾乱』…観応元年(1350)前後)
(実は…、この幕府には、尊氏・直義という賞賛すべき両将軍や、
直義に通じる、多くの清廉な部下たちがいた一方で、
常識も道徳も「何それ、うまいの?」と意に介さぬ、驕りを極めた奴等も当然いた。
(直義だけでは扱い切れない事もあろう)彼らの事は、これまで主に尊氏が上手く手なずけていたのですが… )
この辺りはもう本当、鬱展開ですね。
私は直義の性格が好きなので、考えるたびにヘコみます。
(※この時期、幕政を主導していたのは基本的に直義で、
尊氏は、将軍としての部下への「恩賞」など、一部に関わりつつも、
世務を譲ったのちは、あくまで直義を立てていました。
一見、「あれ?どっちが将軍なの??」と思わずにはいられない二人の関係ですが、
この辺の権力構造の話はちょっと複雑で、文献等を提示しながら詳細に説明しなければならない所なので、
とりあえず今、一言で表現しておくと、
「将軍としての "存在" は尊氏にあり、将軍としての "実権" は直義にあった」
…或いは
「 "本質" としての将軍は尊氏であり、"実質" としての将軍は直義だった」
といった感じです。(分かり難くてすみませんw)
もちろん、単に「将軍」と言ったら尊氏のことを指し、それは揺るぎない事実なのですが、
ただ、幕府誕生までの過程を足利勢の視点で描いた『梅松論』で、
転戦する軍勢を率いる二人を「両大将」「両御所」とセットで呼んでいる事が多く、
その後も、公家や僧侶の日記や記録で「将軍兄弟」「両将軍」などの表記が目立つ事から、
周囲の目には、二人は並列に近い存在にも映っていたようです。
特に、儀式的なこと(例えば、国家的な慰霊の法会など)では、二人は相並んで臨席していて、
一体不可分の関係にあったと言えます。
ちなみに…
尊氏は、諸侍から絶大な人気があり、政務執行能力も十分にあったのに、なぜ世務を直義に譲ったのか?
なぜ遁世を望みつつ、しかし将軍であり続けたのか?
…といった問題は、これまで必ずしも深く追求されて来ませんでしたが、
(なぜって、余りに意味不明で、解明不能だったからw)
しかし、よくよく考察してみたところ、
あの「清水寺の願文」の謎も含め、「尊氏七不思議」のほとんどが解けました。
(嘘のようですが本当ですw 私も驚きました。)
尊氏の、一見適当すぎる成り行き任せの生き様にも、実は理由があったのです。
後述の『観応の擾乱』の真相と共に、近く解説する予定です。 ―――2014.12.29追記 )
直義が政務に励んだ十数年、
幕府は制度基盤を整え堅実な政治を実現し、 世の中は正しい方へ進んで、都では文化もいよいよ興隆し、
動乱の世は、終わりを迎えつつあったように見えたのですが、
同時に、幕府内に小さな亀裂が育ちつつあったなんて、しかもそれが、この兄弟の別れに発展するなんて、
そんな物語、誰が想像出来たでしょうか。
しかし、これは決して、
"兄弟の確執" とか "主導権争い" といった問題として理解されるべきものではありません。
(従来の一般的な説はそうですが。)
上述のように、尊氏は自ら望んで直義に世務を譲ったのだし、
直義は「再三辞退した」のちに、尊氏の「懇望」とあって了承したのだし(『梅松論』)、
また、直義は常々
「家(家柄・生まれ)によって身を立てようと思っていはいけない。
文道(学問)を嗜み、徳を身につけることで身を立て、
御代(=尊氏)の御助けとなるように」 (『難太平記』)
と、周囲に語っていたように、
直義自身、兄である尊氏を「支え助ける」という意識が強かったのです。
つまり―――
尊氏と直義は、「兄弟で将軍権力をめぐって争いをするような関係では無い」のです。
また、直義の政道に対する姿勢、
天下を大局的に捉え、壮大な理想を描くような思考の持ち主であることを鑑みても、
兄に対する対抗心や、まして権力への執着に突き動かされて、
道を誤るような人間ではないことは明らかです。
…まあ、そう考えると益々やり切れなくなってくるんですがw
(※『観応の擾乱』は、実は、詳細に検討するとかなり意外な真相を秘めた事件です。
尊氏が "直義との抗争を優位に進めるため" に、南朝に対して "戦略的に降伏した"
とされている、いわゆる『正平一統』についても、
時系列に重心を置いて史料を分析すると、全く違った答えが弾き出されます。
(この時の尊氏の行動は、一見非常に軽率で、
厚恩のある持明院統(北朝)の天皇・上皇に対する裏切りにすら見え、
これまで従順に仕えて来た尊氏の態度からすると、本当に意味不明なのですが、
それもそのはず、従来の解釈に誤りがあったのです。)
おそらく、『観応の擾乱』はその開始理由からして、
根本から描き直される事になるかと。
これについても、別途解説する予定です。 ―――2014.12.29追記 さらに2015.1.11追記)
歴史上、"兄弟の骨肉の争い" なんていくらでもあるじゃん、と言えばそうなのですが、
大抵は、「異母兄弟でもともと疎遠だった」「争うべくして争った」…という場合がほとんどだと思います。
元来こんなに仲が良く、動乱の世を生死を共にして生き抜き、同母の兄弟でしかも、
生涯互いを思い遣っていた二人が最後にこの展開、
というのは、おそらく他に例がないんじゃないかと…。
それに比べたら、最終的には仲直りできたあの兄弟は、幸せだったと思います。
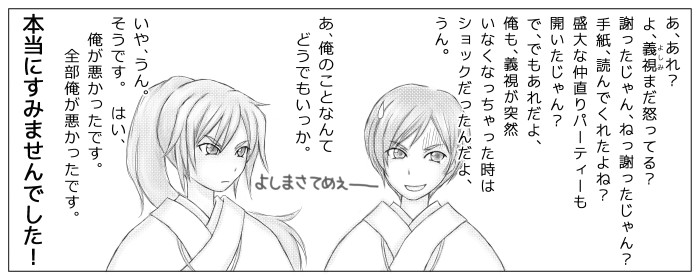
(※義政・義視…『応仁の乱』辺りの、足利兄弟。)
そんな動乱の世も、尊氏のあとを継いだ2代目足利義詮(よしあきら)の治世の後半には、
徐々に静謐を取り戻しつつありました。
都に平穏な日々が戻り、幕府の体制が整って、公方(=将軍)の地位が安定してくると、
京都はいよいよ繁栄し、3代目足利義満の治世では、
室町幕府は少し遅れた春の、満開の花に包まれる時を迎えるのです。
「始まった未来」
さて、ここまでが室町時代の初期、南北朝期ともいわれる時代です。
鎌倉幕府が倒れ、
建武の新政が時勢に合ったものだったら、その方向で天下は流れて行くことになったのだろうけど、
そうでなかった為に武家政権が再度立ち上がり、
しかも今度は、その拠点を朝廷と公家の都、京都に定めます。
東国を本拠地とし、武家は武家、公家は公家、という方針だった鎌倉幕府に比べて、
室町幕府はスタートの時点で、既にかなりフリーダムです。
どうなってしまうんでしょうか。
(…いやまぁ、色々と大変なことになってしまうんですけどね、これからね。)
ちなみに、場所を何処にするかのくだりは『建武式目』に記述されています。
「やっぱ、武家政権は鎌倉だよね! でもちょっと不吉かな?」 (←驕りを極めた前政権が滅亡した場所だから)
「いや、正しい政道を行えばいいんだよ。場所のせいじゃないよ!
武家の聖地・俺らの鎌倉は今でも吉!!」
「そっか、だよね! じゃあ、一応みんなの意見も聞いとこうぜ」
で、京都に決定!! …って、なぜ!?
よく分かりませんけど、まぁそういうことです。
以上、室町幕府創生期から3代目義満期まで、もっと詳しく知りたい方は、
【佐藤進一『南北朝の動乱』(中公文庫)1974】
を読みましょう!
(※この本が刊行されたのは50年近く前なので、以後の研究成果で変化・訂正のあった部分も所々ありますが、
それでも今なお、この時代を描いた歴史書の最高傑作です。)
それから、足利直義に興味を持った方は、
【羽下徳彦『中世日本の政治と史料』(吉川弘文館)1995】 …の p.120-p.223
をどうぞ。
まあ他にも色々ありますが、
足利直義については、まともな歴史専門書なら、賞賛してないものは無いと言っても過言ではないほど、
武士中の武士と言うに相応しい、最高に清々しい精神を持った稀有なやつです。
(その上、本当にめっちゃめちゃ頭が良いw
史実を知れば知るほど、誰しも讃えずにはいられなくなる人物です。)
あとそれから、この幕府の意外(?)な特徴として、
「乱世に対して非常に深い痛みを抱き、強く天下泰平を祈り続けていた」
という点が挙げられます。
それは、尊氏・直義という二人の将軍と深い関係にあった、夢窓疎石という禅僧との三人による事業であり、
そして、持明院統(北朝)の光厳上皇をも交えた、"国家的な祈り" でした。
詳細は、この先少しずつ語っていくことになると思いますが、
彼らが残した偉大な業績、そしてどれほど深い祈りを捧げ続けていたか…
参考文献だけ挙げておきますので、興味がある方はどうぞ。
【西山美香『武家政権と禅宗 ――夢窓疎石を中心に』(笠間書院)2004】 …の、Ⅰ部「初期室町政権と夢窓疎石」
初代将軍足利尊氏と足利直義は、
どのような理想を抱き、どのような未来を願っていた将軍だったのかは、
初期の室町幕府を考察する上で根幹となる、最も重要な視点です。
さて最後に、「室町幕府創生期」の事跡を記した当時の記録としては、
『太平記』『梅松論』(軍記物ですが、比較的 "公の視点" で描かれているので、参考になります。)
『難太平記』(今川了俊による手記。了俊は良い奴なので、かなり信用できる史料です。)
…などが、代表的なところです。
一般に軍記物は、その記述が真実である保証は無いので(中には、ホントに酷いものもあるw)、
他の史料と突き合わせて慎重に検討した上で用いなければならないものですが、
当時を知っている人々によって書き継がれた『太平記』は、よく世相を反映しているし、
それよりさらに成立年代が早い『梅松論』は、
現存の軍忠状と照らし合わせてみると、かなりの信憑性の高さが認められます。
…まあ、『太平記』がだいぶ潤色されまくっているのは事実ですがw
(『太平記』は、基本的に乱世という時代に対して悲観的であり、それ故批判的なのですが、
一方で、救いのない時代に救いを見出すべく、事実を美しく叙述しようする意図が見られ、
その為、やや(いやかなり)情緒的になっているのです。)
確かに注意は要しますが、この時代(特に幕府誕生以前)は他に史料が少ないので、
全く参考にしないと言うのでは、それこそ真相は永遠に闇の中となってしまう訳で、
『太平記』『梅松論』と、現存の古文書(書状)、貴族や僧侶の日記等を総合して、最も妥当な線をたどれば、
真実を導き出す事は可能でしょう。
それに、当時の人々の感じ方、社会の捉え方を知るという意味では、非常に貴重な史料と言えます。
(ちなみに、『太平記』は室町幕府の検閲が入っていて「足利家に都合の良い様に書き換えられている!」
などという言いがかりを付けられていますが、
『太平記』は今川了俊が証言しているように、
「此の記の作者は宮方深重の者(=南朝方に精通した者)」であって、第三者目線が保たれているし、
"宮方深重" ゆえ「(足利方に)無案内にて押して此の如く書きたるにや」(『難太平記』)とあるように、
「足利方の事を良く知らなくて、無理矢理想像で書いてしまっている」部分があったのです。
つまり―――
『難太平記』に、「直義が、『太平記』の誤った記述を改めるように指示を出した」とあるのは、
文字通り「真実に反する記述を正しく修正するように」という意味であって、
「足利家に不利な事を削除しろ!そして書き換えろ!」なんて、せこい事する卑怯な幕府じゃありません。
尊氏にしろ、直義にしろ、室町幕府は史上稀に見る素直な将軍の幕府です。
こんなにも道義ある政道を目指して始まった幕府、本来なら、最も誇れる日本の歴史であるはずなのに、
それなのに…
なぜ近代になって突如、
室町幕府は「最低の逆賊」だと声高に叫ばれ、そんな歪められた歴史が信じられ、
自らの国の正しき武士たちを、憎み蔑む事になってしまったのか?
その理由は…次のページで。)
それから『梅松論』は、
足利方の人物によって書かれただろうもので、やや贔屓目にはなってはいますが、
それでも、二人の大将に、命を惜しまず忠節を尽くす家臣たちや、
それに相応しい資質をもって、彼らを率いる両将の存在感には、
成り行きで天下が導かれたのも納得…と思えてしまいますw
(幕府誕生以前の時代を語る『梅松論』や『難太平記』の部分には、
二人の将軍が天下を取る未来を暗示する、数々の「奇瑞」(きずい)があった事が記されていて、
偶然ではない流れに導かれていたのだろうか…と考えさせられます。
(※奇瑞…めでたい事の前兆として現れる不思議な現象) )
まあ、適宜参考にしてみて下さい。
(ちなみに私は、全て原文だけで読破…なんて殊勝なことはしていません。すみません。)
ああ、それにしてもこの時点でまだ、15世紀初頭…メインの時代までまだ半世紀もある。
続きは、「3 続々・室町幕府の前半戦」で!