小見出し
「国の始まり」
「日本の神話」
「武士の誕生」
「お待たせ室町幕府」
1 室町幕府の前半戦
このサイトでメインに取り上げるのは室町時代の中盤以降ですので、
それ以前の幕府の状態について、なんとなく説明してみたいと思います。
…と、その前に。
いきなり室町時代だけ取り上げても、イメージ掴み難いことこの上ないですね。
その前にも後にも、時代は存在しています。
世界最長レベルのこの国の歴史の連続性を意識しつつ、
ここらで一度、思い出を整理しておきましょう。
「国の始まり」
さて、どこまで遡りましょうか。縄文・弥生時代は…戻りすぎですかね。
まぁでも、そのくらいから思い起こしてみると、
「なんだかんだ言って、俺らも成長したよなぁ」とか、感慨深くなれていいですね。
それが、紀元前はるか昔(1万数千年前)から紀元2〜3世紀あたりです。
…と言っても、実はこの時代も思った以上に文化や生活のレベルは高かったようで、
近年の発掘調査によって、なんか色々凄かったらしい事が考古学的に明らかにされつつあります。
(…細々と原始人的な生活をしていた…とか言うのは勘違いだったらしいw
特に縄文時代は、日本人のルーツを秘めた大変興味深い時代です。 各自いろいろ調べてみよう!)
まあ、人間は社会性を持つ知恵ある動物ですからね、生きてりゃ色々な事に気付いて来るのは当然な訳で、
「あれ、おまえまだ木の実拾ってんの? 稲育てようぜ、稲!」とか
「あれ、俺ら協力すれば、もっとでかい建物造れるんじゃね?」
…と、そんな感じで、
初めは小さな集落に過ぎなかった共同体は、やがて村になり、
規模が大きくなれば自然と「まとめ役」も必要になってきたりして、
なんか長老っぽい人のもと、私たちはぬるい日常の中にも、着実な進化を遂げて行きます。
大陸から伝わってきた文明にしばしば加速されながら、
いつしか、そこには王国が!!
…邪馬台国とか大和王権(=大和朝廷)とか、古代王朝 真っ盛りの時代ですね。
時期にして5〜6世紀前後まで、今から1500年は前の話です。
(※ごく初期の段階では複数の王国が並立、それが徐々に統合され、一つの国家へと成長して行きます。)
ちなみにこの頃、西日本を中心に各地にせっせと古墳が作られたので、古墳時代といいます。
日本最大(墳丘では世界最大!)の規模を誇るのは、大阪府堺市の『仁徳天皇陵』!!
そして、第二位は同じく大阪府の… あ、これテストに出るので覚えておいてください。
(※テストに出る=このサイトの他のページで話題にされる。)
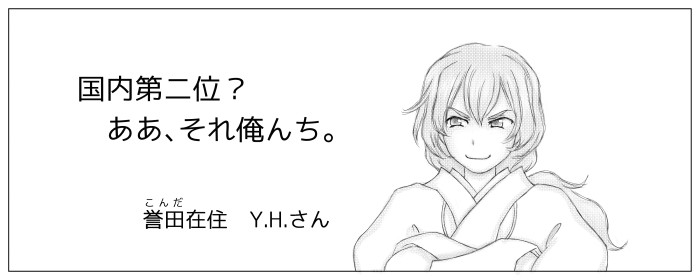
(※Y.H.さん…室町時代の人)
いやはやそれにしても、
ぼっちでキノコ拾ってた私たちが、成長したもんですね。感涙です。
でも本来、社会や国が形成されていく過程なんて、こんな風に、ごく自然なものなんですよ。
人間てのはそういう生き方をするもの、ってだけの話です。
つまり、国の本質は "その土地に生きる人々そのもの" なのであって、
別に、わけ分からん権力だとかシステムではないってことです。本来はね。
さて、国が人だというのなら、それは私たちの成長と共に姿を変えて行くことになる訳で、
試行錯誤を繰り返しながら続けてきたその変化が、
私たちの生きてきた道、すなわち、この国の「歴史」という訳です。
覚えていないようで、でもたどればいつでも蘇る、長い長い歴史の道です。
何百何千年と、記憶は "私たちの頭" を渡り歩いて今日まで続いてきました。
逆に、自分の中の思い出を遡れば、数百年前のあの人に繋がっている、
だから、歴史はいつだって楽しくて懐かしいのです。
さて、話を元に戻して。
スライムが合体してキングスライムになった所でしたね。
そしてこの後、皆さんご存知のように、王国は更なる変貌を遂げます。
そうすなわち、スライムエンペラーによる皇国へとリビジョンアップするのです!!
(…すみません、若干不敬罪っぽくてごめんなさい。本当にごめんなさい、パルプンテ!)
(※ちなみに、君主の称号が大王(おおきみ)から天皇(すめらみこと)へと変化しただけであって、
王朝が断絶したり交替した訳ではありません。)
という訳で、天皇を戴くこの国は、
朝廷を中心とした「貴族の治める世」として、繁栄を遂げていくことになります。
だいたい7世紀が飛鳥時代、8世紀が奈良時代、9〜12世紀が平安時代と、
都の置かれた場所にちなんでそう呼びます。
さらっと流してしまいそうになりますが、この間、600年ですよ。平安京だけでも400年。
律令制が整い中央集権的な国家体制が確立していくと同時に、
日本っぽい文化が本気出してきます。
かな文字の発達、和歌、各種物語をはじめとした文学、これらはどれも今に通じますね。
どうやら、千年経っても根本的な感性は変わっていないようなので、
当時の作品を改めて見直しながら、「こ…これが、千年前の俺ら…」とか思ってみましょう。
「日本の神話」
こうして、社会はより大きく複雑になっていく訳ですが、
そんなある日、美しく整った都を眺めながら私たちはふと考えました。
「なんか、俺らもだいぶ凄いことになってきたし、この辺でそろそろ生い立ち整理しておこうか」
という訳で、この国の成り立ちを記した歴史書『古事記』『日本書紀』の誕生です。
これが、奈良時代(8世紀)の初めのことで、『古事記』は "現存する" 日本最古の書物でもあります。
これらの「国史」は、それ以前から朝廷に伝わる書物や各地の伝承をかき集めて編纂されたものですが、
初めの初め、国の誕生を記したいわゆる『日本神話』の部分は…珠玉の出来ですw
まあ、記紀の内容は、断片的にならみなさん知っていると思いますが(※記紀(きき)…古事記+日本書紀のこと)、
出来るだけ妄想全開で読んでみると、面白さが倍増していいですね。
「ちょ、神様ww 何やってんすかww」…みたいなね。
このふざけ…失礼、個性的で愛すべき神様たちが私たちの祖先なんですよ、知ってました?
なんかちょっと楽しくなって来るでしょ。
(ちなみに、日本 "神話" と言っても、勝手に作った完全おとぎ話…という訳ではありません。
日本神話の元となったのは、太古においては人々が口頭で伝え継いで来た先祖の伝承です。
まだ文字が無い遥か昔の時代、
人々は自分達の過去や起源、つまりこの国の歴史を、"神話" という形で言葉で語り継いでいたのです。
口伝であるが故、長く伝えられる間に変化が加わり、
若干(いやかなり)荒唐無稽な感じになってしまってはいますが、
あくまで、事実から生まれた話なのです。
そういう意味では、「先祖が神」と言うより、大昔は「"遠い先祖" を神と呼んでいた」と言った方が的確です。
"日本の神の物語" とはすなわち、"日本のご先祖様の物語" って訳です。)
ちなみに、もし『日本神話』を全然知らないという方がいましたら、
この機会に是非一度読んでみて下さい。
手軽に入手出来る文庫本なら、例えば…
【中村啓信訳注『新版 古事記 現代語訳付き』(角川文庫)2009】
【宇治谷孟『日本書紀(上・下)全現代語訳』(講談社学術文庫)1988】
とか。 まあでも、今はネットで検索するだけでも十分な知識が得られると思います。
ところで、この国で最もやんごと無い日の女神様といえば天照大御神(あまてらすおおみかみ)ですが、
その弟の須佐之男命(すさのをのみこと。素戔嗚尊とも)も、個人的にはかなり一押しです。
なんか、乱暴だとか凶暴だとか言われていますが、あれ実は誤解なんすよ。(いつか擁護解説する予定w)
(記紀の記述は、全てが史実と言える訳ではないのは当然ですが、
まあ、基本的には「素直に伝承を元にしている」と言えると思います。
というのも、奈良時代になって "新たに" 作られたものだったら、
もっと筋の通ったフィクションになっててもいいはずなのに、
普通に考えると(特に前半部分は)、なんかかなり荒唐無稽な話なのでw
(なんか意味分かんない伝承だけど、まあ、そう言い伝えられてるからそう書いとくか、
…みたいな感じだったのかと。)
しかし一方で、なんとなく不自然な加筆・編纂の跡が見受けられるのも事実で、
神話部分では、特にスサノヲ命関連はかなり…(以下略)
ただし、ちょっと注意して読めば割とバレバレですので、
「どんな意図によるものか?」という視点で読むと、また面白いのです。)
そんな訳で、多少のハチャメチャ感と、若干の創作跡があるのも確かなので、
盲目的になるのは問題がありますが、
この国に生まれたからには、一度は「自分達のルーツ」に思いを馳せてみて下さい。
(…というか、「室町幕府のサイト」と言いつつ、
実は、先々この「日本神話」部分も絡んで来る予定ですので…よろしくお願いします。)
遥か昔の物語ではありますが、
どれだけ時間が経とうとこの「謎多き古代のロマン」は、きっといつだって、
真新しい好奇心を掻き立ててくれる事でしょう。
(『古事記』や『日本書紀』は、その性質から非常に多くの謎を秘めていますが、
それによって、歴史書としての価値が損なわれる、という訳ではないし、
(むしろ、その謎にこそ価値があるのが『日本神話』だったりする… )
「古代の人々は、世界をどう捉え、どんな営みを繰り返してこの国を形成して来たのか?」
という視点を持って、
想像の世界に、古(いにしえ)の自分達を再現してみる事は、有益な事だと思います。
まあ確かに、意味不明だったりコーヒー噴きそうになる記述が無い訳ではありませんが、
まずは、"物語" として親しんでみる事をお勧めします。
(どんなにシュールな話にも無粋な突っ込みは無用です。
あふれ出すコーヒーに耐えるのが「記紀道」(ききどう)です。)
その上でもし、記紀の魅力に目覚めてしまったのなら、
今度は "純粋な学問" として挑んで見るといいと思います。(いよいよ突っ込み解禁です。)
まあ、記紀の謎解き議論は、正直言って9割方「トンデモ陰謀論の不思議系分野」になってしまっていますがw、
実は一方で、非常に真面目な研究も進んでいるのです。
確かに、学問として捉える記紀は、何となくロマンに欠ける…と言うか、
国の神話の分析は…偏った主観やいらぬ思想を持ち込まれそうで危険過ぎるww…と、
私も以前はやや敬遠していたのですが、
しかし、高い客観性を保って深められた学術研究は、決してそんな事はありません。
むしろ、そこで明かされつつある「本当の日本と日本人の姿」には、
今まで以上に誇らしさを感じることでしょう。
(…と、少なくとも私は思います。 この辺の事は、いずれ改めて言及する予定ですが、
日本の古代に関しては、実は『記紀』だけでなく、
各地方の『風土記』、神社の「縁起」、古代豪族の「系図」などなど…
これまで日陰に隠れて重視されずにいた貴重な史料が多く存在し、人知れず真相を語っているのです。)
まあもちろん、
実証手段の極めて乏しい大昔の事ですから、どうしても、
「研究者ごとに諸説乱立、どれを信じるかは君次第!」…みたいな所も無きにしも非ずですが、
しかしそれでも、"歴史学" として、
あくまでも「真実の探究」を目標に信念を持って挑めば、
最も妥当な仮説…すなわち、古代の真実(と思われるもの)に、たどり着けるはずです。
学問の世界に "諦め" は不要。 不可能を想定してしまったら、何も発見できません。
謎に秘められた可能性を探るのが学問ですからね。 宇宙に挑む物理学みたいにね。
(それに、健全な学問としてみんなで守っていかないと、
極一部の人たちによって唱えられたマイノリティー突き抜ける珍説によって、
知らない間に、「○○は本当は居なかった!」とか言って、勝手に否定&上書きされていたり、
変なものにこじつけられたり、変な起源を捏造されたりして、
この国の始まりが、無残に汚され蹂躙される…
という、常識では考えられない事態が発生してしまいます。
…ってゆうかもう発生してるww いやあぁぁーーー!!!wwww)
という訳だ。
物語としてでも良し、学問としてでも良し、
みんなもどんどん、誇りを持って記紀の妄想学に参加しよう!
脳内妄想もいいけど、関連する神社めぐりも楽しいよ! はまり過ぎて時空超えそうになるよ!)
ちなみに、この国の "すべてはここから始まった" 場所は、『オノコロ島』です。
ここに伊耶那岐命(いざなきのみこと)と伊耶那美命(いざなみのみこと)が降り立って、
淡路島から順に「日本列島」を生んでいった訳です、云々。
この島は "架空の島" とも "実在の島" とも言われていますが、
候補の一つに、淡路島の南に位置する沼島(ぬしま)がという島が… あ、ここもテストに出るよ。

(※公方(くぼう)…将軍のこと。 この人も室町時代の人。)
「武士の誕生」
さて、またまた話を戻して。
この時代は、地方に広がる国衙領(公領、国有地)や荘園(貴族や寺社の私有地)から、
政治の中心である都(みやこ)に税が集められる中央集権的な社会として発展していきますが、
都が栄えれば、地方だって成長します。
地方の豪族や農民たちが力をつけてくれば、ほっといても都に税が集まる時代ではなくなってくる訳です。
うーむ困った。どうしよう。
そこで、地方の統治のため、中央から武装した武官たちを派遣することにしました。
しかし、やはり全てを中央(都)の思いのままに出来る時代は終わっていて、
ある程度は、"その土地の者たち" に "その土地のこと" を委ねざるを得なくなってきます。
この流れと相俟って、先程派遣された武官の中には、そのままその土地に残って勢力を拡大していく者が現れました。
これが「武士の起こり」、
だいたいこの時代の半ば、10世紀頃のことです。
こうしてみると、武士というものは「武芸に秀でたもの」というだけでなく、
「地方に広がり、土地と結びつく志向性を持つ」ということも重要な特質の一つと言えるでしょう。
(※「武士の起こり」については、未だ不明な点も多いのですが、
「社会的身分(階級)としての武士」という(限定的な)意味ならば、
その起源は、まあ平安時代の武官に求めることが出来ると思います。
…というのも、
この国には既に遥か太古の昔から、
「土地に根差し、武芸を身につけ、君に仕える者」という武士の先駆的な存在、すなわち、
"古代豪族" が各地に根を下ろしていたからです。
彼らは大抵、神話の時代まで遡れる起源を持ち、大国主(おおくにぬし)の時代はもちろん、
天皇が大王(おおきみ)と呼ばれていた頃から仕え、共にこの国を形作って来た重要な存在なのですが、
かつては国の主役であったその勢力も、長く続いた「貴族の世」の間に昔日のものとなっていました。
しかし―――
時代がくだり、中央から派遣された武官が、在地の彼らと結びつく事で、
再びその存在感が高まると共に、新たな意義が課せられ、
やがて一つの社会的階層を築くほどの特異な存在へと、成長して行く事になったのでしょう。
…なぜ彼らは、単なる武官(朝廷の役人)あるいは地方の一豪族という状態で終わらずに、
「武士」という特別な種族へと変貌を遂げたのか?
それは恐らく、彼らが武力や武芸だけではなく「 "理念" をも身に付けた存在だったから」、
…だと思いますが、
まあ、この辺の事(武士の本質、この国における武士の存在意義など)については、
この先、しつこく言及していく予定。)
さて、武士といえば、みんな大好き "源氏" と "平氏" ですね。
もちろん、他の流れを汲む武士も沢山いましたが、やはり皇族出身の彼らは特別な存在でした。
地方の武士団を統率し、『武家の棟梁』となって隆盛の道を歩んで行く事になる訳ですが、
(特に源氏は、東国武士団との繋がりを強めていきます)
元々は朝廷に仕える武官ですから、やはり本来の地盤は都(京都)な訳で、
やがて、朝廷に対して強い影響力を持ち、12世紀中葉以降(平安時代末期)
栄華を極めることになるのが平家(平氏の一流)であります。
しかし、盛者必衰は世の常、平家は源氏によって滅亡の日を迎えます。
この功績により、源頼朝は東国における支配権を認められ、
鎌倉幕府の成立、武家政権の始まりへと繋がって行くのです。
こうして、長く続いた "朝廷が政治の中心であった時代" が終わりを告げ、
"武家が政権を担う時代" が始まります。
といっても、初めの頃は「京都の朝廷」に対する、武家による「鎌倉(東国)の地方政権」
という性格が強かったようですし、
朝廷だって、政権の全てを譲るつもりだったのではありませんが、
承久3年(1221)の『承久の乱』(朝廷による討幕作戦、失敗に終わる)を経て、
この公家から武家への流れは、再び引き返すこのない確固たる潮流となっていくのです。
こうしてみると、
「ああ、嘆かわしや、古の栄えし都…」と遠い目をしたくなる公家の気持ちも分かりますが、
ただし、これをもって単純に、天皇の権威の失墜だとか衰退だと言ってしまうのは、少し違います。
(そもそも、これまでも朝廷で政権の主要部分を掌握していたのは、
公家の藤原氏だった訳で(※公家は大部分が藤原氏)、
天皇の外戚として朝廷の中枢で一体となって政治を司る藤原氏と比べて、
武家である源氏は本来、天皇との関係では、むしろより厳密な君臣関係にありました。
奈良・平安の藤原氏の長い繁栄を経て、
平安末期の平家が極めた刹那の栄華とともに、「政界を一族で占める時代」が終わり、
それと代わる様に、源氏による「武士の時代」が始まったのは、
"歴史の必然" だったんじゃないかと、私は思います。)
つまりあくまで、時代の流れに即した「変化」あるいは「進化」として、
天皇の位置付けは、"直接政治は執らないけれどその上に君臨する" という、より高次の段階に「昇華」した、
言い換えれば、権力の中心から距離を置いたことで、
相対的に国の象徴としての権威が、一層堅固なものとなった訳です。
別に誰かがそうしようと思ってそうしたのではない、ごく自然な社会の成熟として。
そして、そういう地位に昇ったからこそ、
この国の歴史は、以後何百年途切れることなく一本に繋がって行くことになるのです。
(事実、時の政権を握る者がどうしょうも無くグダグダで、「ちょ、えっ、この国終わる?!」
みたいなピンチは歴史上何度かありましたが、それでもこの国がこの国であり続けられたのは、
グダグダ政府の上位に、天皇の存在があったからです。 いやホント、セーフセーフ。ありがてぇ!)
朝廷(天皇、公家)と武家政権の関係については、
たまに、異民族かのように敵対的に捉えようとする考え方がありますが、
武士の本質を考えれば、その捉え方には大きな誤解があります。
だいたい、もし武家が天皇に "仕えるもの" ではなくて "敵対するもの" だったら、
つまり、「武家が朝廷から政権を奪い取った」と解するならば、
その時点で、普通に考えたら朝廷は滅んでいるはず、
先代の世(貴族の世)は、文化もろとも殲滅の運命です。
…しかし、そうはなりませんでした。
皇統も伝統も、始まったときから、その悠久の流れを途切れさせることが無かったのは、
今もなお、歴史が証明し続けています。
つまり、公家の時代も武家の時代も、古来一貫して天皇が君主である事に変わりはなく、
そのもとで、あくまで公家と武家は共存しつつ、"主役の座" が武家に移って新たな時代が始まった、
貴族の世は滅んだのではなく、武家の世と調和して、共に歴史を綴り続けていったのです。
例えば文化に関しても、古いものと新しいものとが "混在" するのが日本文化の特徴ですが、
もし、「古いものを捨てて、新しいもので置き換えていく」ということを繰り返していたら、
日本文化というものは、今よりずっと魅力の無いものになっていたでしょう。
…なぜなら、長い時間をかけて積み重ねて来た伝統は、それ自体の尊さもさることながら、
新たな文化を生み出し続ける "源泉" でもあるからです。
伝統というものが、古いだけではなく最先端にもなり得る、という事実は一見矛盾するようですが、
室町時代に生まれた文化が、今も全く色褪せることなく、
私たちを惹きつける "何か" を常に持ち続けていることを思い起こしてみると、実感出来ると思います。
室町の文化――それは、京の"雅な公家" と、東国鎌倉の "質素・堅実な武家" とが、
"京都という地" で出会い融合することで誕生した独創的な文化であり、
今に繋がる日本文化の源流ともいえる、唯一無二の幽玄な世界なのです。
「お待たせ室町幕府」
さて、ようやく室町時代の影が見え隠れしてきました。
12世紀末に源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから約150年、14世紀も三分の一が過ぎた頃、
私たちは "次の扉" を開くことになるのです。
ところで、源氏と平氏といえば気になるのは「源平交代思想」。
「やっぱ平氏の次は源氏なんでしょ?でしょ?」 っていう、政権交代の都市伝説です。
平安時代末期に源氏が平氏を討って
→源頼朝が鎌倉に幕府を設立。しかし源氏の将軍は3代で途切れ
→その後は摂家・皇族将軍を立てて北条一族(平氏)による執政。
つ、つまり次は…
ってことで期待に応えちゃいました、源氏出身足利家、尊氏さんの登場です。
うむ、確かに見事に交代していますね。
でも、元来は「源氏と平氏は相並んで王朝の守りに任ずる」ものだったそうですよ。
それがいつしか変貌して、この頃(1330年代)には既に、源平の交代伝説は生まれていたようです。
実際に源氏または平氏の血を引く武家による政権は、この足利家による室町幕府までなので、
そうすると、源氏大勝利!って感じですね。
…うん、まあその、それはそうなのですが、
室町幕府の歴代将軍は確かに足利氏なんですけど、源氏と平氏の関係で言えば、なんというか、
これまでにない不思議な、なんとも "室町幕府らしい" 絶妙な関係が繰り広げられていたようです。
さて、やっと本題に…って、前置き長すぎました。
すみません、続きは「2 続・室町幕府の前半戦」で!